【最新】食品工場の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!最も電気代を安くする方法も紹介
.jpg?width=800&height=313&name=banner-w800h313-9-%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B7%A5%E5%A0%B4%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)
電気代の高騰や省エネ法の施行などにより節電の必要性を感じつつも、具体策がわからないという食品工場の経営者や担当者の方も多いのではないか。
節電により運営コストを削減できれば、利益改善にもつながる可能性が高い。
そこで、本記事では食品工場で節電・電気代削減する際のポイントや、具体的な節電方法を解説していく。
|
この記事でわかること
|
食品工場で節電・電気代削減する際のポイント

|
結論をまとめると 食品工場で節電・電気代削減に取り組むポイントは以下の3つ |
まずは、食品工場で節電と電気代削減に取り組む際に知っておくべきポイントを解説する。食品工場の電力の使用状況や電気代高騰の理由を知ることで、より効率的に節電できるようになるはずだ。
関連記事:業務用電力とは?単価や電力会社の選び方、産業用電力との違いをわかりやすく解説
関連記事:【図解】節電ポイントとは?仕組みと申し込み方法、注意点を解説!企業にメリットはある?
①食品工場の電力使用量の内訳
1つ目のポイントは、「食品工場で何にどれだけ電力を使用しているか」だ。以下は、一般的な工場の電力使用量の内訳である。

上のグラフから、工場では「生産設備」の電力消費量が8割以上を占めているとわかる。つまり、食品工場で節電に取り組む際には、「生産設備」を最優先にすると効果が出やすい。
特に食品工場では冷蔵・冷凍庫など電力を多く消費する生産設備があるため、それらを集中的に節電するといいだろう。
関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法を徹底解説!
②食品工場の電力使用パターン
2つ目のポイントは、食品工場の電力使用パターンだ。食品工場では、日勤の時間帯(9時〜17時)に最も電力消費量が増える。これは24時間稼働しているタイプの工場でも同じだ。
さらに、1年を通して見ると夏季と冬季に電力使用量が増える。夏季と冬季には、外気や湿度による影響を受けやすい空調・換気の消費電力が上がるからだ。
つまり、食品工場で節電する際には、夏季・冬季の日中に特に力を入れると効果が出やすくなる。
関連記事:【図解】特別高圧とは?電気代の仕組み、低圧や高圧との違い、活用メリットをわかりやすく解説!
③なぜ電気代が上がっているのか
3つ目のポイントは、電気代が上がっている理由だ。
電気代の高騰は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻で、世界的に燃料価格が上がったことがきっかけとなっている。日本では火力発電の割合が高いため、発電に必要な燃料価格の上昇の影響を受けて電気代も値上がりしたのだ。
さらに、政府の補助金の終了や再エネ賦課金などの要素も加わり、現在電気代は高止まり状態である。今後、燃料価格が大幅に下がる見込みはなく、電気代が下がる可能性は低い。そのため、食品工場で電気代の負担を減らしたい場合、節電による電気代削減が効果的となるのだ。
関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!
食品工場の「製造・搬送機器」の節電・電気代削減方法

|
結論をまとめると 食品工場の「製造・搬送機器」の節電・電気代削減方法は以下の6つ |
ここまで、食品工場で節電・電気代削減のポイントを解説してきた。これらのポイントを踏まえた上で、ここからは具体的な節電方法を説明していく。
まずは、先述したように食品工場の電力消費量の8割以上を占める「生産設備」にあたる製造・搬送機器の節電方法を見ていこう。
関連記事:【最新】倉庫の節電・電気代削減方法とは?法人がすべき節約術をわかりやすく解説!
関連記事:【法人向け】動力とは?電気料金の仕組みや電灯との違いをわかりやすく解説!
①機械の稼働スケジュールを調整する
最初の食品工場の節電方法が「機械の稼働スケジュールの調整」だ。
例えば、稼働スケジュールを調整することにより、機械が稼働していない間も発生する待機電力やアイドリング稼働を減らせば、約10〜20%の節電・電気代削減になる。
また、機械は起動時に最も消費電力が大きくなるため、起動時間を分散させれば、ピーク電力を抑えられる。電気代の基本料金はピーク電力で決まるため、機械のスケジュール調整によって、使用分の電気代だけではなく基本料金も削減できるのだ。
②使わないライン・機械の主電源をオフする
次の節電方法は、使わないライン・機械の主電源をオフにすることだ。これにより、食品工場の電力使用量のうち約3〜8%を占めている「待機電力」を削減できる。
ちなみに、待機電力とは機械が主電源につながっているだけでも発生する、わずかな電力のことだ。食品工場では、特に包装・充填ラインで稼働時間外も制御盤やコンベヤモーターが通電している場合が多いため、主電源のオフを意識するといいだろう。
なお、電源タップやブレーカー制御を取り入れると、エリアやライン単位でスイッチを一括操作しやすくなるのでおすすめだ。
③搬送コンベヤやモーターをインバーター化する
「搬送コンベヤやモーターのインバーター化」も食品工場の節電になる。インバーターとは、モーターの回転速度を自由に調整可能にする装置のことだ。
例えば、モーターの回転速度を10%落とせば、約27%の節電・電気代削減になる。これは、通常オンオフしかない機械をインバーター化したことにより、フル稼働させずに必要なだけの出力で運転できるようになるからだ。
特に食品工場ではインバーター化で製品の量に応じて搬送コンベヤの速度を調整したり、製品サイズや量によって包装・充填ラインのモーターを制御したりすると節電に効果的だろう。
④潤滑剤や調整で機械抵抗を減らす
潤滑剤や調整で機械抵抗を減らすことも、食品工場の節電に効果的だ。
食品工場の機械では、回転や搬送などのあらゆる部分で摩擦・軸ずれ・固着などの機械抵抗が発生する。これらの機械抵抗が増えると、同じ動作を行う際にも、より多くの電力を消費するようになり電気代が高くなるのだ。
潤滑剤や調整によって機械抵抗を減らせば、5〜10%の節電・電気代削減ができる可能性がある。具体的にはモーター動力を使用する機械には潤滑剤を使用し、チェーンやベルトの張力調整や機械の速度・圧力・温度の見直しを行うといいだろう。
⑤デマンド監視装置を導入する
次の節電方法は、「デマンド監視装置の導入」だ。デマンド監視装置とは、使用電力のピーク値をリアルタイムで監視・制御するものである。
法人の電気料金は、使用電力のピーク値によって基本料金が決まる。そのため、ピークになりそうなときに自動で設備を調整するよう、デマンド監視装置で設定すれば、基本料金を約10〜20%削減できる可能性があるのだ。
また、デマンド監視装置で機械の不要な同時稼働や待機運転も削減できるので、さらなる節電・電気代削減につながる。
関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!
⑥定期的に設備点検・メンテナンスを行う
定期的に設備点検やメンテナンスを行うことも、生産設備の節電になる。
具体的には約5〜10%の節電・電気代削減が期待できるだろう。なぜなら、設備の劣化や汚れにより機械の性能が落ちると、余分な電力を消費するようになるからだ。
例えば、月1回の軽点検と年1回の精密点検というスケジュールを設定し、機器を点検・清掃するといいだろう。また、点検の際には、摩擦・振動・漏れ・温度・異音などの項目をチェックリストにしておくと確認漏れを防げる。
食品工場の「冷凍・冷蔵設備」の節電・電気代削減方法

|
結論をまとめると 食品工場の「冷凍・冷蔵設備」の節電・電気代削減方法は以下の7つ |
ここまで、食品工場の「製造・搬送機器」の節電方法を解説した。
その他に生産設備の中では「冷凍・冷蔵設備」による消費電力が多い。そのため、ここからは「冷凍・冷蔵設備」の節電・電気代削減方法を説明していく。
関連記事:【最新】冷凍倉庫の節電・電気代削減をわかりやすく解説!最も電気代を抑える方法も紹介
関連記事:【最新】飲食店の節電・電気代削減方法とは?法人がすべき節約術をわかりやすく解説!
①設定温度を適正化する
1つ目の冷凍・冷蔵設備の節電方法は、「設定温度の適正化」だ。
冷凍・冷蔵設備は温度を下げるほど電力を多く使用する。そのため、設定温度を1℃上げると冷凍庫は約2〜4%、冷蔵庫は約3〜5%節電・電気代削減できるのだ。
ただし、温度調整する際には、冷凍・冷蔵設備はHACCP(国際的な衛生管理システム)の基準を遵守する必要がある。「冷蔵食品は0〜10℃」「冷凍食品は-20〜-18℃」などの基準を守った上で、品質に影響がない範囲で温度を調整するといいだろう。
②冷却器・圧縮機にインバーター制御を導入する
2つ目は冷却器・圧縮機にインバーター制御を導入することだ。これにより、約15〜30%の節電・電気代削減になる。
先述したように、インバーター制御とは、モーターの回転数を自動で調整する機能だ。熱を外へ放出し、冷気を庫内に循環させる「冷却器」と、冷凍・冷蔵サイクルの心臓部となる「圧縮機」にインバーター制御を取り入れると、これらの機器を必要なときに最適スピードで稼働させることができる。
例えば、外気温が低く負荷が小さい夜間や冬季は圧縮機を低速運転にしたり、冷却器のファンの回転数を下げたりする設定にしておくと、効率よく節電ができるだろう。
③搬入口の開放時間を短縮する
3つ目が、搬入口の開放時間を短縮することだ。
冷凍・冷蔵庫内は、搬入口を開ける際に外の空気が侵入し、庫内の温度が上がってしまう。搬入口の開放時間が長いほど、設定温度に戻すために余分な電力・電気代が発生するのだ。
だが、手動でもドアの開閉を最小限にすれば、約5〜10%の節電・電気代削減になる。さらに、高速シャッターの導入で約10〜20%、エアカーテンの併用をすれば約5〜10%の節電が期待できるだろう。
④デフロストの回数を最小限にする
次の冷凍・冷蔵設備の節電方法は、デフロストの回数を最小限にすることだ。
デフロストは、冷却効率を落とす霜が溜まることを防ぐ重要な機能だ。しかし一方で、デフロスト自体の電力消費量が大きく、行う度に庫内の温度が上がるため、温度を戻すのにも電力が必要となる。そのため、デフロストを最小限にすることにより、約10〜20%の節電・電気代削減が期待できるのだ。
例えば、センサー連動型に変更すれば、霜が発生したときだけデフロストを行うため無駄な稼働を防げるだろう。センサーの導入費用などは、約1〜2年で回収できる可能性が高い。
⑤定期的に清掃・メンテナンスを行う
定期的な清掃・メンテナンスも、冷凍・冷蔵設備の節電に効果的だ。これにより、約10〜20%の節電・電気代削減になる。
冷凍・冷蔵設備では、圧縮機や冷却器で熱を移動させることで庫内を冷やしている。これらの機器にホコリや汚れが溜まると熱の伝わりが悪くなるため、庫内を冷やすのに余分な電力と電気代が発生するのだ。
なお、清掃・メンテナンスの頻度は、以下を目安にするといいだろう。
- フィルター清掃:1ヶ月に1回
- 蒸発器・ファン清掃:3ヶ月に1回
- 凝縮器フィン清掃:3〜6ヶ月に1回
- 冷媒漏れ点検:6ヶ月〜1年に1回
⑥霜・結露対策を徹底する
次に、霜・結露の対策を徹底することも重要だ。冷凍・冷蔵設備に霜や結露がつくと、冷却効率が落ち、無駄な電気代が発生する。そのため、霜・結露を防ぐことで約20〜30%の節電・電気代削減になるのだ。
具体的には、搬入口の開放時間を減らして湿気の侵入を防いだり、除湿機を併用して庫内の空気中の水分を減らしたりして、霜を抑制するといいだろう。
また、霜の発生を防げば先述したデフロストの回数を抑えることにもつながり、さらに節電ができる。
⑦老朽化した設備を更新する
冷凍・冷蔵設備の節電方法の最後が、「老朽化設備の更新」だ。最新の冷凍・冷蔵設備は10年前の設備と比べ省エネ性能が優れており、2倍近く消費電力が少ない。そのため、設備を更新するだけで、約40〜50%の節電・電気代削減になるのだ。
また、老朽化により設備の性能が低下していた場合、さらに大きな節電効果が得られる可能性がある。設備の更新には費用がかかるが、約2〜4年で費用を回収できるケースが多い。
食品工場の「空調設備」の節電・電気代削減方法

|
結論をまとめると 食品工場の「空調設備」の節電・電気代削減方法は以下の8つ |
ここまで、食品工場の生産設備の節電方法について解説してきた。
次に、食品工場の消費電力量の約1割を占める「空調設備」の節電・電気代削減方法を紹介する。電気代が高額である食品工場では、1割とはいえ節電によって一定のコスト削減が期待できる。
関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!
関連記事:【最新】商業施設の節電方法をわかりやすく解説!法人におすすめの電気代削減方法とは?
①空調の設定温度を見直す
最初の空調設備の節電方法は、空調の設定温度を見直すことだ。例えば、冷房は1℃上げると約13%、暖房は1℃下げると10%の節電・電気代削減になる。
ちなみに環境省では、室温を夏季は28℃、冬季は20℃に設定することを推奨している。これはあくまで目安であり、難しければ設定温度を1℃調整するだけでも節電効果が得られるのだ。
②エリアごとに空調設定を調整する
次の節電方法は、エリアごとに空調設定を調整することだ。これにより、空調の20〜35%の節電・電気代削減が期待できる。
食品工場では、全館一括の空調制御であることも多く、使っていない部屋まで冷暖房してしまっている。人がいないエリアは空調を停止し、稼働エリアは場所ごとに温度を調整するといいだろう。なお、エリアごとの温度設定の目安は、以下が参考だ。
| エリア | 冷房 | 暖房 |
| 一般加工エリア | 26〜28℃ | 18〜20℃ |
| 個装・梱包エリア | 27〜29℃ | 17〜19℃ |
| 冷蔵準備室・低温加工室 | 10〜15℃ | 10〜15℃ |
| 事務所・休憩室 | 27〜28℃ | 19〜20℃ |
③サーキュレーターを併用する
サーキュレーターを併用することも、節電に効果的だ。これにより、約5〜15%の節電・電気代削減が期待できる。
食品工場は天井が高い建物が多く、温度ムラが大きくなりやすい。そこでサーキュレーターを空調と併用することによって、温度ムラを解消し、空調効率をよくすることができるのだ。空調効率がよくなれば、空調の設定温度を1〜2℃調整しても快適に過ごせるだろう。
また、サーキュレーターは、冷気・暖気が溜まりやすい天井や窓際に設置すると効果的だ。
④フィルターや熱交換器を定期的に清掃する
次の節電方法は、フィルターや熱交換器を定期的に清掃することだ。
食品工場は粉や油、蒸気などが空気中に舞いやすいため、空調フィルターや熱交換器が汚れやすい環境となっている。しかし、汚れが溜まると空調の効きが悪くなり、無駄な電力と電気代が発生してしまう。
定期的に清掃をすれば、空調効率の低下を防ぎ、約20%の節電・電気代削減になる。なお、清掃頻度は、フィルターは1ヶ月に1回、熱交換器は6ヶ月〜1年に1回を目安にするといいだろう。
⑤窓に遮熱フィルムや遮熱コーティングを導入する
食品工場の窓に遮熱フィルムや遮熱コーティングを導入することでも、節電効果が期待できる。
遮熱フィルムや専用コーティングは、窓ガラスから入ってくる日光で室温が上昇することを防ぐ。そのため、夏場の冷房効率が上がり、年間では約5〜10%の節電・電気代削減になるのだ。
なお、遮熱フィルムを導入する際には、暗くなりすぎないよう可視光透過率60〜80%のものを選ぶといいだろう。
⑥屋根や外壁に断熱・遮熱塗装を行う
さらに、屋根や外壁に断熱・遮熱塗装を行うことも、節電になる。これにより、約15〜40%の節電・電気代削減が期待できる。
まず、遮熱塗装は屋根や外壁の表面で日射の赤外線を反射するものであり、夏季に建物内の温度が上がるのを防ぐものだ。一方、断熱塗装は熱が伝わるのを遮断するため、夏・冬問わず建物内が外気温の影響を受けることを抑えられる。どちらも併用するとより効果が高まる。
特に屋根の面積が広い食品工場では、屋根からの放熱が大きいため、断熱・遮熱塗装の効果が得られやすい。屋根・外壁あわせても費用は約2〜4年で回収できる可能性が高く、効果は10年以上持続するため、長期的な節電対策をしたい場合におすすめだ。
⑦空調制御システムを導入する
次の節電・電気代削減方法は「空調制御システムの導入」だ。自動で空調を制御することで、約20〜30%の節電になる可能性が高い。
例えば、空調制御システムを導入することで、稼働時間外の空調を自動停止できる。また、温度や湿度などに応じて出力設定を自動で調整することも可能だ。さらに、最大消費電力が上昇しそうなタイミングで出力を抑えることで、電気代の基本料金が上がることも防げる。
また、多くの場合、空調制御システムを導入した費用は3年以内で回収できるケースが多い。
⑧古い設備を更新する
古い設備を更新することも、大幅な節電が期待できる。最新の空調設備は、古い機器に比べて約20〜40%も省エネ性能が高い。そのため、10年以上前の機器を使っている場合には、新しい機器に買い替えることで節電・電気代削減ができるのだ。
なお、買い替えにかかる費用は、約3〜5年で回収できる可能性が高い。また、新しい設備にすることで劣化による突然の故障も防げる。夏場に空調が故障すると作業がストップする要因となるため、生産停止リスクを下げるためにも、設備の更新は有効なのだ。
食品工場の「照明設備」の節電・電気代削減方法

|
結論をまとめると 食品工場の「照明設備」の節電・電気代削減方法は以下の7つ |
ここまで、食品工場の「製造・搬送」「冷凍・冷蔵」「空調」の節電方法を解説してきた。
食品工場では「空調」とほぼ同じ割合で「照明」で電力を消費している。そこで、ここからは「照明」の節電・電気代削減方法を紹介していく。
関連記事:電力需給のひっ迫はなぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げリスクも!概要と法人がすべき対策を解説
関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
①照明をLEDに替える
1つ目の照明の節電方法は、LED照明へ替えることだ。
LED照明は、蛍光灯より約50%、白熱灯より約80%も消費電力が少ないため、器具を交換するだけで大幅な節電・電気代削減が期待できる。また、LEDは発熱が少ないため、特に冷凍・冷蔵庫内の照明に使うと、冷却設備の節電にもなるのだ。
さらに、LEDは蛍光灯や白熱灯と比べ長寿命で、交換頻度は10分の1以下に減る可能性が高い。
②照明をこまめにオンオフする
2つ目の照明の節電方法は、「こまめなオンオフ」だ。食品工場では、休憩時間やライン停止中にも照明がつけっぱなしになっていることが多い。そのため、人がいないエリアの照明を消すだけでも、約10〜20%の節電・電気代削減になる。
例えば、「退出時には必ず消灯」と工場内に掲示をして従業員に消灯を呼びかけたり、つけっぱなしがないかの見回りスケジュールを組んだりすると、費用をかけずにすぐに節電効果が得られるだろう。
③照度を見直す
3つ目は、照明の照度を見直すことだ。食品工場では、必要以上に照明が明るくなっている場合も多い。その場合、適正な明るさにすることで、約10〜30%の節電・電気代削減になる可能性が高い。
照度を調整する際には、以下を目安にするといいだろう。なお、照明の明るさはlx(ルクス)という単位で表される。
- 仕分けエリア:400〜600lx
- 製造ライン:300〜500lx
- 検査・包装エリア:750〜1,000lx
- 倉庫・出荷エリア:100〜200lx
④照明を間引きする
照明を間引きすることでも、約20〜50%の節電効果が期待できる。
例えば、明るすぎるエリアの照明は1灯おきに点灯し、通路や搬送ラインはメインの導線だけ点灯してサブ通路は消灯するなど、必要最低限な明るさに調整するといいだろう。
照明を間引きする際には、先述した照度の目安を参考に、暗くなりすぎないようにする必要がある。なお、照度を測る際には照度計があると便利だ。
⑤人感センサーやタイマーを利用する
次の照明の節電方法は、人感センサーやタイマーを利用することだ。これにより、照明の30〜50%を節電・電気代削減できる。
例えば、通路や倉庫、休憩室は滞在時間が短いため、照明のつけっぱなしによる無駄が発生しやすい。また、トイレも人の出入りが多く、手動によるこまめな消灯が難しい。このような場所には人感センサーを導入すると、無駄な電気代の発生を抑えられる。
また、出荷エリアや搬入口は稼働スケジュールにあわせてタイマーで消灯するように設定すると、消し忘れを防げる。
⑥自然光を活かす
自然光を活かすことも照明の節電になる。窓から自然光を取り入れることで、日中の照明を部分的に消灯できるため、約20〜40%の節電・電気代削減になる可能性があるのだ。
また、自然光は目が疲れにくく、作業の品質向上も期待できる。
なお、自然光を活かして節電したい場合、照度センサーと自動調光機能のある照明を設置するとより効果的だ。費用の回収は約2〜3年が目安となる。
⑦定期的に照明器具を清掃する
さらに照明を節電するなら、定期的な照明器具の清掃が効果的だ。
照明器具を清掃しないでいると、ホコリや油膜によって光が遮られ、年間で照度が約20〜40%も落ちる。定期的な清掃によって明るさを保つことで、約10〜20%の節電・電気代削減になるのだ。
なお、照明の清掃頻度は以下を目安にするといいだろう。
- 揚げ物・惣菜ライン:3ヶ月に1回
- 製造・包装エリア:6ヶ月に1回
- 倉庫・通路・事務室:1年に1回
食品工場の「その他」の節電・電気代削減方法

|
結論をまとめると 食品工場の「その他」の節電・電気代削減方法は以下の5つ |
食品工場の各設備の節電方法について紹介してきたが、それ以外にも節電できる部分がある。節電効果を最大にしたい場合には、その他の節電にも取り組むといいだろう。
そこで、ここからは食品工場の「その他」の節電・電気代削減方法を解説する。
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
①給湯温度を調整する
まずは、給湯温度を調整することだ。給湯は設定温度を1℃下げるだけで、約2〜3%の節電効果がある。食品工場では、大量のお湯を使用するため、給湯温度を最適化すれば年間で約5〜15%の節電・電気代削減になる。
なお、食品工場の給湯温度の目安は以下の通りだ。とりあえず熱めに設定されている場合、適正温度に見直すといいだろう。
- 手洗い:40〜45℃
- 機器・器具洗浄:55〜60℃
- CIP洗浄:60〜70℃
②使わない機器のコンセントを抜く
2つ目が、使わない機器のコンセントを抜くことだ。製造・搬送機器の「使わないライン・機械の主電源をオフする」の項目でも説明したように、電化製品は使わない間も待機電力を消費している。
食品工場には、製造機器の他にもOA機器や計量器、検査機器など多くの機器がある。使わないときにこれらの機器をコンセントから抜くだけで、約3〜5%の節電・電気代削減になるのだ。
また、コンセントの抜き忘れを防止するために、電源チェック表を作成し、就業時にコンセントを抜ける電化製品を1つ1つ確認していくといいだろう。OA機器などはスイッチ付きのコンセントにすると簡単に制御できるようになる。
③自動販売機の設定温度を見直す
次の節電方法は、自動販売機の設定温度を見直すことだ。過度に冷却・加温している場合に適正な温度にすることで、約10〜30%の節電・電気代削減が期待できる。
具体的には、加温は60〜66℃、冷却は5〜8℃に設定するといいだろう。また、夏季は加温・保温を停止し、冬季は冷却を停止することも電気代を抑えるコツだ。
さらに、タイマーを導入して夜間や休日に自動停止する設定をするとより節電できる。
④温水洗浄便座の温水・便座温度を下げる
温水洗浄便座の温水・便座温度を下げることによっても、節電・電気代削減ができる。
例えば、温水の温度設定を「高」から「中」にすれば約15〜25%、便座温度を「高」から「中」にすれば約10〜20%の節電効果が期待できるのだ。また、夏季と夜間、休日には加温をオフにしておくとより効果的だ。
⑤太陽光発電設備を導入する
最後の節電方法は「太陽光発電設備の設置」だ。食品工場は屋根面積が広い施設が多く日中に稼働する施設が多いため、太陽光発電を導入すれば、自前で発電した電気を使用して電気代を大幅に削減できる可能性が高い。
また、太陽光発電設備は、地形や日射量のデータをもとに影が発生しないよう設計することで、発電の効率を高められる。そのため、施工してもらう事業者選びにはこだわろう。

なお、しろくま電力は、店舗の屋根や駐車場に設置するソーラーカーポートなど、国内の太陽光発電設備の施工を多く担当してきた。グリーンエネルギーの発電・送電・売電に特化した電力会社であり、設備の設置からメンテナンス、売電まで一気通貫で担当している。
太陽光発電設備を検討している場合には、ぜひ「しろくま電力」にお気軽にご相談いただきたい。
関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!
関連記事:自家消費型太陽光発電とは?導入するメリットやデメリットをわかりやすく解説
最も効果的な食品工場の節電・電気代削減方法とは

|
結論をまとめると
|
ここまで、食品工場の節電・電気代削減方法を紹介してきた。節電を行う目的は、やはり、「高騰している電気代を安くしたいから」という法人も多いだろう。
電気代を大幅に安くするには、節電以外にも効果的な方法がある。それは、電気料金の単価を安くすることだ。
電気料金の単価は、電力会社やプランによって異なる。そのため、今より単価の安い電力会社やプランに切り替えれば、使用する電気の量は同じでも、電気代を下げることができる。節電と違い、電力会社の切り替えをするだけなので手間も少ない。
電力会社の法人向け電力プランには、以下のようにさまざまな種類がある。
|
このようなプランの中から食品工場の特性に合ったものを選べば、電気代を抑えながらコストの管理も簡単になるのだ。
「大手の電力会社の方が安心だ」と考えている方もいるかもしれない。しかし、新電力の中にも安心して利用できる企業はたくさんある。大手電力会社から新電力に切り替えたとしても、電気の質や停電リスクは変わらない。それどころか、電気代は安くなる可能性が高い。
まだ電力会社の見直しを検討したことがない法人は、一度、新電力に見積もりを取ってみていただきたい。どれくらい電気代が安くなるのかを確認した上で、切り替えを検討してみるといいだろう。
関連記事:【最新】法人の電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解
<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も> しろくま電力で御社の電気代を削減しよう
しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。
しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。
しろくま電力は、商業施設や工場、店舗などさまざまな施設・法人に導入いただき、電気代の削減を実現している。例えば、以下はしろくま電力に切り替えた法人が電気代をどれほど削減できたかの実績の一部である。

さらに、以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

多くの法人から、低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。
また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。
見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。
見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。


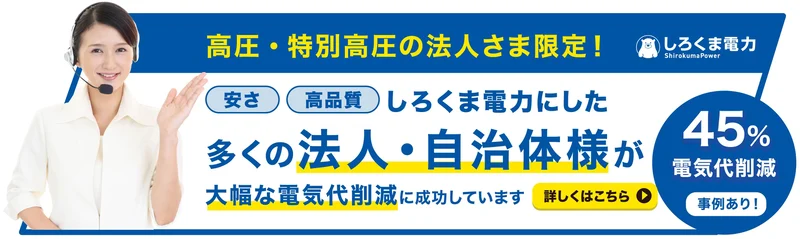
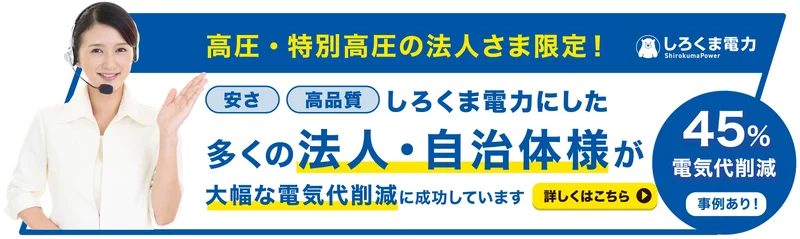
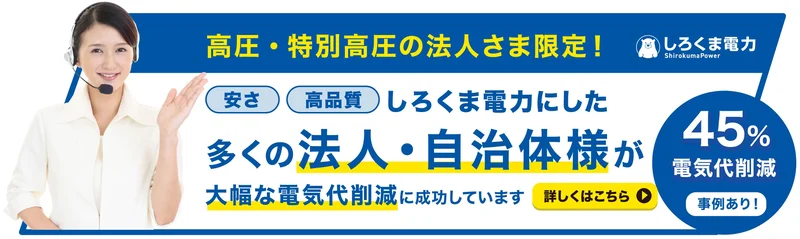
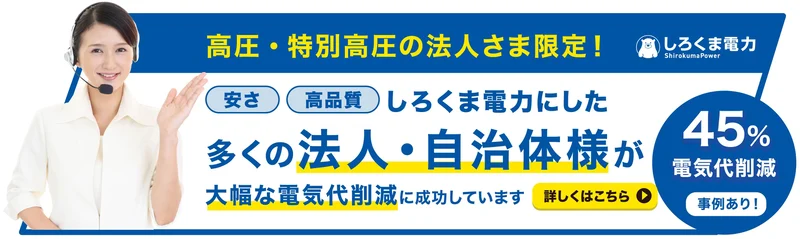
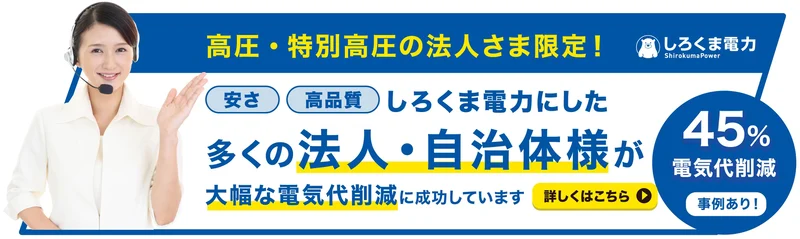
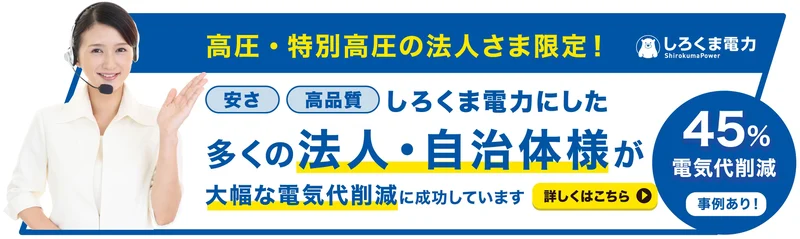
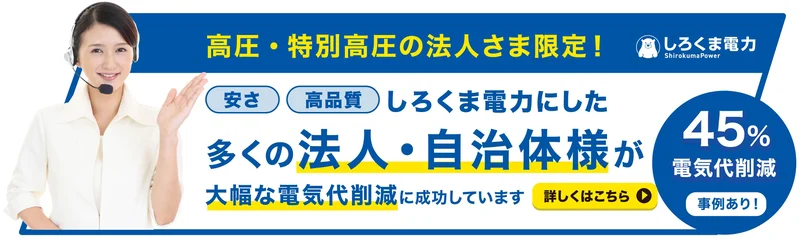
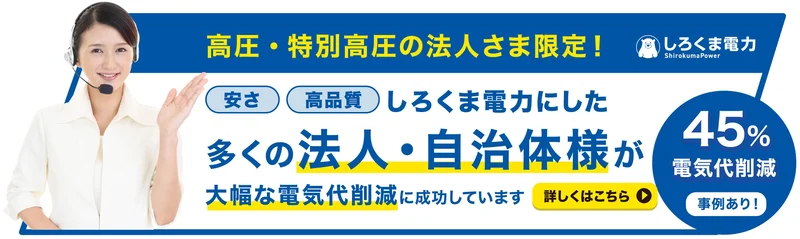
.jpg?height=200&name=banner-w960h540-1-%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)
%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg?height=200&name=banner-w960h540-8-%E5%86%B7%E5%87%8D%E5%80%89%E5%BA%AB(%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%80%89%E5%BA%AB)%20%E7%AF%80%E9%9B%BB(%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E5%89%8A%E6%B8%9B).jpg)
