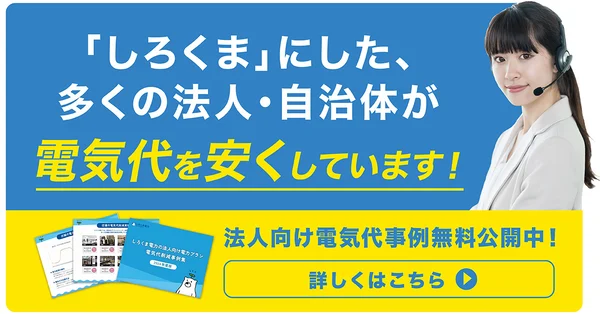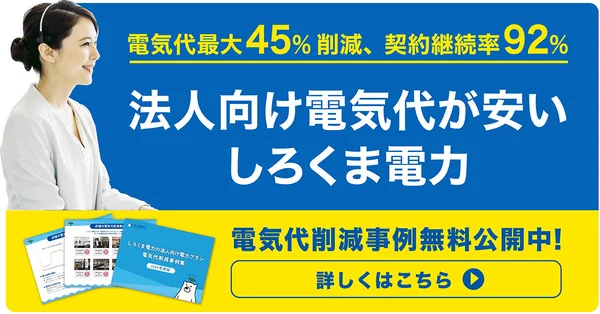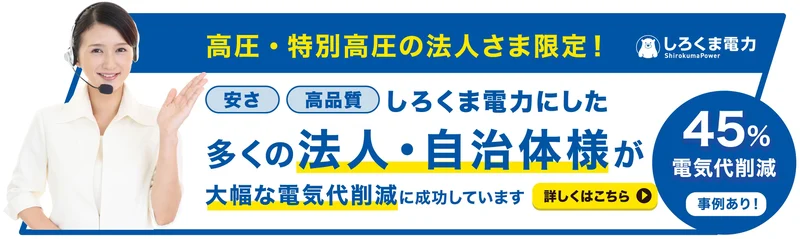【図解】特別高圧とは?電気代の仕組み、低圧や高圧との違い、活用メリットや法人の電気代削減方法をわかりやすく解説!

特別高圧とは、法人を対象とした電力の契約形態のことだ。法人によって、電力の契約形態は、低圧・高圧・特別高圧と異なる。
この記事では、特別高圧の仕組みや低圧・高圧との違い、メリット・デメリット、さらには特別高圧の電気代を安くする方法を紹介する。法人の電力契約の見直しを検討している場合、ぜひ参考にしていただきたい。
関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人ができる電気料金の高騰対策を解説!
関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
|
この記事でわかること
|
|
目次 特別高圧と低圧・高圧の違いとは 特別高圧のメリット・効果 |
特別高圧とは?

|
結論をまとめると
|
特別高圧とは、使用電力が多い大規模な工場やオフィスビル、大型商業施設などの法人を対象とした電力の契約形態のことである。正式には「特別高圧電力」という名称だが、略して「特高」と呼ぶ場合が多い。主な特徴は以下の通りだ。
|
供給電圧
|
7,000V超
|
|
契約電力
|
2,000kW以上
|
|
主な電力の使用対象
|
大規模な工場、大型商業施設、オフィスビル
|
そもそも法人の電力の契約形態は、供給される電圧(V)と契約電力(kW)の大きさによって、低圧・高圧・特別高圧の3区分に分けられている(詳しくは後述)。その中でも特別高圧は、供給電力が7,000Vを超え、契約電力が2,000kW以上の施設・法人を対象としている。
一般的に特別高圧で契約する大規模施設や大企業の供給電圧は20,000V、60,000V、140,000V、場合によっては154,000Vや170,000Vなど、非常に大きいことが多い。
特別高圧は電力の使用規模が大きいため、高い電圧のまま施設まで電気を運ぶ必要がある。通常の配電線では電圧を高いままで電気を運べないため、送電線を直接施設に引き込み、施設の敷地内の変電所で使用に適切な電圧まで下げる仕組みになっている。
関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
特別高圧の電気料金の仕組み

|
結論をまとめると
|
特別高圧に限らず、法人の電気代は一般的に「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」の4つの要素で成り立つ場合が多い。
4つの内訳の内容は、以下の通りだ。
|
基本料金
|
電気の使用量に関係なく毎月定額で発生する料金のこと
|
|
電力量料金
|
使用した電力量に応じて請求される料金のこと
|
|
燃料費調整額
|
火力発電で使う燃料費の変動分を1kWhあたりの単価に落とし込んだもの。単価は毎月変動する。電力使用量に応じて価格が決まる
|
|
再エネ賦課金
|
太陽光発電や風力発電などの「再生可能エネルギー」の買い取りにかかった費用を電気代に反映したもの
|
再エネ賦課金は、正式名称を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。使用電力に応じて価格が決まるが、単価は国が決定するため、電力会社によって単価のバラつきがない。
電気料金の料金内訳は低圧・高圧・特別高圧で同じだが、基本料金の算出方法は契約形態によって異なる。
関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!
関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!
関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!
特別高圧の基本料金について
法人の電気代の基本料金は、契約電力によって算出される。契約電力とは、一度に使用できる最大の電力のことだ(キャパのようなもの)。特別高圧電力は契約電力が2,000kW以上のプランとなる。
法人の電気料金の決め方には契約電力によって主に「アンペア制」「実量制」「協議制」などがあるが、特別高圧は「協議制」が採用されている。
協議制では、以下の要素などを踏まえて、協議を行い基本料金が決定される。
- 使用する負荷設備
- 受電設備の内容
- 同一業種の負荷率
電気料金の基本料金が協議制で決定されるのは、特別高圧と高圧の一部のみである。
関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説
関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説
特別高圧と低圧・高圧の違いとは

|
結論をまとめると 特別高圧と低圧・高圧には以下の点で違いがある①電力設備 ②受電方式 ③電力供給の流れ ④供給電圧と利用される場所 ⑤電気料金 |
冒頭でも説明したように、法人の電気の契約形態には低圧・高圧・特別高圧の3区分がある。区分による違いを以下の図にまとめた。
|
低圧電力
|
高圧電力
|
特別高圧電力
|
|||||
|
電灯
|
動力
|
小口
|
大口
|
||||
|
契約電力
|
~50kW
|
50~500kW
|
500~2,000kW
|
2,000~
10,000kW |
10,000~
50,000kW |
50,000kW~
|
|
|
電気料金
|
アンペア制など
|
実量制
|
協議制
|
||||
|
供給電圧
|
~200V
|
6,000V
|
20,000V
|
60,000V
|
140,000V
|
||
|
主な供給対象
|
家庭・事務所・小規模店舗など
|
飲食店、美容室、町工場など
|
中小規模の工場やオフィスビル、マンション、学校、病院など
|
大規模な工場や大型ショッピングモール、オフィスビル、デパートなど
|
|||
図を見ると、特別高圧は契約電力や供給電圧が低圧・高圧と比べ大きな値であると分かる。さらに特別高圧は、低圧・高圧と比べ主に以下の点に違いがある。
- 電力設備
- 受電方式
- 電力供給の流れ
- 供給電圧と利用される場所
- 電気料金
ここから、低圧・高圧と比較した特別高圧の特徴を要素ごとに解説する。
そもそも低圧・高圧とは?
低圧とは、一般家庭や個人商店、小規模なオフィスなどを対象とした電力の契約形態だ。法律上では、供給電圧が600V以下の場合低圧に区分される。一般的には契約電力が50kW未満、供給電圧が100Vまたは200Vの施設が該当する。
高圧とは、家庭よりも電力を使うが超大型施設ほどは電力使用量が多くない、工場やオフィスビル、商業施設、病院などの中小規模の法人を対象とした、電力の契約形態のことである。一般的には、契約電力が50kW~2,000kW未満、供給電圧が6,600V程度の施設が該当する。
以下の記事ではより詳しく低圧・高圧について説明しているので、こちらも参考にしてほしい。
関連記事:高圧電力とは?低圧や特別高圧との違い、契約の注意点もわかりやすく解説!
違い①電力設備
特別高圧と高圧は、低圧と比べ非常に多くの電力を扱う。しかし、大きな電圧の電力をそのまま施設で使用することはできないため、需要家自身が設置する特別高圧受変電設備が必要となる。
20,000Vまたは60,000V、140,000Vといった大きな電圧のまま敷地に供給された電力は、受変電設備で電圧を段階的に下げて、各施設で使える電圧(400V、200Vなど)にしてから使用するのだ。
例えると、工場から樽で大量に届いたビールを店で提供する際に、ビールサーバーを通してジョッキに注ぐのと似ている。ビールが電力だとすると、受変電設備はビールサーバーの役割を担う。
関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法を徹底解説!
高圧と特別高圧は電気主任技術者が必要
高圧または特別高圧で受変電設備を設置する場合、電気主任技術者の選任が義務付けられている。特別高圧の場合、供給電圧が20,000Vの場合は第三種電気主任技術者が、60,000Vと140,000Vの場合は第二種電気主任技術者の選任が求められる。
高圧の場合は、第三種電気主任技術者を選任しなくてはならない。高圧・特別高圧の電気主任技術者は外部の企業から選任することも可能だ。ただし、外部からの選任であっても、特別高圧の電気主任技術者は事業所内に常駐させる必要がある。高圧では条件を満たせば兼任が認められる。なお、低圧には電力設備は必要ない。
違い②受電方式

特別高圧の受電方法(電力会社から電力を供給してもらう方法)には4つの方法がある。
- 本線予備線受電
- 本線予備電源受電
- ループ受電
- スポットネットワーク受電
本線予備線受電は、同じ発電所・変電所から本線と予備線の2本の送電線を引いてくる方法である。普段は本線を使い、トラブルがあれば予備線に切り替えて受電できる。
本線予備電源受電は、本線と予備線を別の変電所から引く方法である。本線と予備で発電所も送電線も異なるので、地域停電が起こった場合にも稼働するのが強みだ。
ループ受電は、変電所や施設をループ状に送電線でつなぐ方法である。広い敷地に建物が点在するテーマパークや工場の敷地で使用されることが多く、どこか1箇所の経路が切れても反対側から電気を受電できる。
スポットネットワーク受電は、複数の回線(通常は3回線)で受電する方法である。複数回線につなげた変圧器をビルの地下で太い1本の低圧母線に合体させている。どれか1回線が停電しても、残りの回線から受電できるため、停電を防げる。最も停電に強い受電方式だが、導入コストが高い。
なお、高圧は本線単独受電が一般的で、工場やビルでは本線予備線受電を採用する場合もある。低圧は1本の引込線から受電し、電柱や地中の配電変圧器で低圧化した電気を使う。
違い③電力供給の流れ

発電所からの電気は上から変電所を通って下へ流れていく。上流の電気の電圧は高く、変電所をたくさん経由した下流の電気は電圧が低くなる。
特別高圧は上流に位置する一次変電所や中間変電所など上流に位置する変電所から電気を受電する。高圧は特別高圧より下流の配電用変電所で変圧した電気を、低圧はさらに下流の柱上変圧器で変圧された電気を受電する。
特別高圧は、非常に高い電圧のまま電気を施設や敷地内の受変電設備に引き込んで使用する仕組みだ。特別高圧の受電設備で事故が発生すれば、下流の施設にも影響がある可能性があるため、特別高圧施設では、電気主任技術者の選任や定期的なメンテナンスを通し、安全に運用できるよう努める必要がある。
違い④供給電圧と利用される場所
特別高圧は供給電圧が7,000Vを超えるものと定義される。一般的には20,000V以上の契約が多く、一時変電所や中間変電所で変圧された電力が、大規模な工場、大型商業施設、オフィスビル、空港などが該当する。
高圧は供給電圧が600Vを超え7,000V以下と定義される。一次変電所、中間変電所を経て、さらに配電用変電所で変圧された電力が、中小規模の工場やオフィスビル、商業施設、病院などが該当する。
低圧は供給電圧が600V以下と定義される。各変電所で減圧された電力を電柱で受電し、柱上変圧器でさらに100Vや200Vに変圧して、一般家庭や個人商店、小規模なオフィスで使われる。
関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を解説!電気代を削減しよう
違い⑤電気料金
特別高圧は、電気料金の傾向においても低圧・高圧と違いがある。先ほど紹介したように、電気料金の内訳は「基本料金」「電力量料金」「燃料費調整額」「再エネ賦課金」の4つから成り立つ。
特別高圧は、基本料金が電力会社と需要家が協議する「協議制」で決定される。それに対し、高圧の一部は「協議制」だが、他の高圧は過去12ヶ月の30分ごとの電力使用量の最大値を基に基本料金が決定される「実量制」で決まる。また、低圧は契約アンペア数に応じて基本料金が決定される「アンペア制」であることが一般的だ。
多くの電力を使用する特別高圧は高圧・低圧と比べ基本料金が高く、単価が割安に設定されていることが多い。一方、低圧は高圧・特別高圧と比べ基本料金が安く単価が高くなる傾向がある。
関連記事:【最新】法人の電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!
関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
特別高圧と低圧・高圧の違いをまとめると
特別高圧と低圧・高圧の違いについて、ここまで説明してきた内容をまとめると以下のようになる。
|
低圧
|
高圧
|
特別高圧
|
|
|
電力設備
|
不要
|
高圧受変電設備
|
特別高圧受変電設備
|
|
電力設備の運用
|
不要
|
第三種電気主任技術者
|
第二種以上の電気主任技術者
|
|
受電方式
|
電柱上の柱上変圧器から
直接引き込む |
本線単独受電または
本線予備線受電 |
・本線予備線受電
・本線予備電源受電 ・ループ受電 ・スポットネットワーク受電 |
|
電力供給の流れ
|
下流
|
中流
|
上流
|
|
供給電圧
|
600V以下
|
600V超~7,000V以下
|
7,000V超~
|
|
利用施設
|
一般家庭・個人商店・小規模オフィスなど
|
中小規模工場・オフィスビル・商業施設・病院など
|
大規模工場・大規模商業施設・大型オフィスビル・空港など
|
|
基本料金
|
アンペア制など
|
実量制または協議制
|
協議制
|
|
電気料金の傾向
|
基本料金が安く単価が高い
|
低圧より基本料金は高いが単価は安い ただし、特別高圧と比べると単価は高い
|
基本料金が高く単価が安い
|
特別高圧・高圧は受電家が自前の電力設備で変圧してから電力を使用するが、低圧は電力会社が変圧した電力をそのまま使用できる。
特別高圧受変電設備は、難易度の高い第二種以上の電気主任技術者の資格保有者が運用しなくてはならない。高圧変電設備は、特別高圧よりも運用の難易度が下がり、第三種電気主任技術者の資格保有者が運用するよう定められている。
特別高圧は低圧・高圧と比べ、電圧が高い電力を扱うため、放電や停電などのトラブルが起これば、周辺設備や近隣住民など広範囲へ影響が及ぶ可能性が高い。そのため、特別高圧の需要家は、電力会社と協力しながら特に慎重な管理・運用を行う必要がある。
関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!
特別高圧のメリット・効果

|
結論をまとめると 特別高圧のメリット・効果は以下の3つ①電気代が割安になる可能性が高い ②安定供給が期待できる ③送電ロスが少ない |
特別高圧で契約をすると、大容量の電気を受電することならではのメリットがある。主なメリット・効果を見ていこう。
①電気代が割安になる可能性が高い
特別高圧で契約すると、電気代が割安になる可能性が高い。高い電圧で大量に受電することにより、電力会社の送配電コストが減り、電気料金の単価を低圧・高圧より低い水準で設定できるからである。
特別高圧で契約すると、一般的には低圧・高圧より基本料金と電力料金単価が下がる。
特別高圧は設備投資や設備の維持管理コストがかかるが、電気代が割安になるため、電力使用量が大きい施設では、高圧より特別高圧で契約した方が年間コストが安くなるのだ。
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!
②安定供給が期待できる
特別高圧では、安定した電力供給が期待できる。
特別高圧は上流の変電所から直接受電し、需要家が自前の電力設備で変圧した電気を使用する。上流の変電所から受電することで、他の需要家の影響を受けにくい上、自然災害や故障による配電・送電設備の事故から物理的に距離を置けるため、敷地内に電力を安定供給できる可能性が高い。
さらに、受電方式が「本線予備線受電」「本線予備電源受電」「ループ受電」「スポットネットワーク受電」と複数あり、停電してもすぐ別のルートに切り替えられる。結果として、特別高圧では停電リスクを最小限に抑えながら、膨大な電力を安定的に供給できるのだ。
関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!
関連記事:自家消費型太陽光発電とは?導入するメリットやデメリットをわかりやすく解説
③送電ロスが少ない
送電ロスの少なさも、特別高圧の特徴だ。電力は、流れる電流が小さいほど、経路抵抗による送電ロスが少なくできる仕組みとなっている。流れる電流が大きいと、配電の発熱や電圧降下によって送電ロスが発生する。
電圧が高いほど、同じ電力を送るのに必要な電流を少なくできる。特別高圧は低圧・高圧と比べて圧倒的に高い電圧で受電するため、変電所から需要家までの送電ロスが最小限に抑えられる。送電ロスの少ない特別高圧は、エネルギー効率が高く、省エネにつながるといえる。
関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説
特別高圧のデメリット・注意点

|
結論をまとめると 特別高圧のデメリット・注意点は以下の3つ①初期費用が高くなる場合が多い ②保安規程の制定と届け出が必要 ③電気主任技術者の選任が必要 |
特別高圧はコストや管理の難しさにおいて、知っておきたい注意点がある。ここでは、特別高圧のデメリット・注意点を解説する。
①初期費用が高くなる場合が多い
特別高圧のための設備がない場合には、導入時の初期費用が高額になる。
特別高圧の導入には、遮断器や変圧器、保護リレー、受変電盤などを含む大規模な特別高圧受変電設備の設置が必要だ。設備の設置の際には建屋や鉄構、油受けピット、耐火・耐震構造などの付帯工事も発生する。そのため、初期費用だけで数千万円から数億円規模になることも珍しくはない。
特別高圧では電気料金が割安になるが、電気料金の削減によって初期費用が回収できるかといった資本計画を念入りに行うことが重要だ。
関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説
②保安規程の制定と届出が必要
特別高圧で契約する際には、保安規程の制定と届け出が必要だ。
特別高圧の受変電設備は、高電圧を扱うため、危険性も高い。そのため、電気事業法にて、特別高圧設備の設置者は独自の保安規程を作成し、所轄の産業保安監督部へ届け出ることが義務付けられている。独自の保安規程には、「保安点検の周期・方法」「異常時の通報体制」「遮断器の操作手順」などの詳細な運用ルールを盛り込まなければならない。
保安規程を作成する際には、法令や日本電気協会の基準に照らし合わせながら妥当性を確保するなど、専門知識が求められる。また、設置者は、設定した保安規程に従って、受変電設備の維持・運用を保安するために定期的な点検を行うことが課されている。
特別高圧受変電設備の故障によって停電が起きれば、自社の施設の営業や製造が停止し、経済的な損失が発生する。さらに、周囲の住宅や工場、交通機関など、広範囲に渡って影響が出る場合もある。規模によっては多額の損害賠償を請求されるリスクもあるため、保安管理を徹底し、安全を確保しなければならないのだ。
③電気主任技術者の選任が必要
特別高圧設備を保有する場合、保安規程の制定だけではなく、常駐する電気主任技術者の選任も必要である。
電気主任技術者の資格は以下の3種類あり、それぞれ扱える電圧が異なる。
- 第一種:すべての電圧
- 第二種:170,000V未満の電圧
- 第三種:50,000V未満の電圧
原則として、特別高圧の受変電設備を設置する場合、第一種または第二種電気主任技術者を選任し、保安を監督させる義務がある。知識のない人が想定外の事故に巻き込まれることを防ぐため、特別高圧受変電設備に近づけるのは、資格保有者だけである。
しかし、第二種以上の電気主任技術者の資格保有者は希少で、採用の難易度が高く、第三種以下の電気主任技術者と比べ、採用コストや給与などの経費が大きくなる。
社内で資格保有者を確保できない場合は外部企業から選任することとなり、人件費や委託費はより増えると想定される。低圧・高圧と比較し、特別高圧では設備管理において恒久的に発生するコストが大きくなる点には注意しなくてはならない。
関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!
関連記事:【最新】商業施設の節電方法をわかりやすく解説!法人におすすめの電気代削減方法とは?
特別高圧電力の電気代を安くする方法

|
結論をまとめると
|
特別高圧電力の電気代を安くしたい場合、電力会社の切り替えが有効だ。電力小売の自由化により、高圧法人は電力会社の切り替えができるようになった。
現在「大手電力と契約している」という法人も多いかと思うが、大手電力はどの企業でも契約できる分、料金プランが画一的で、あまり電気代のコストパフォーマンスがよくない可能性がある。
なにかと物価高が叫ばれる今、法人にとって大切なのは、自社に合った、かつ安い電力プランを選び、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。
例えば、以下のように法人の特徴によって適した電力プランは異なる。
|
など、法人によって選ぶべきプランは異なるのだ。現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」は、多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。
どうしても「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。
電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」場合もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、まず見積もりをとり、最安の電力会社・プランを選ぶとよいだろう。
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
関連記事:【法人向け】電気代の削減方法を徹底解説!電気料金を安くしたい企業がすべき対策とは
<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>
御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう
しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。
電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。
以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。
しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。
また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。
見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。
見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、「しろくま電力の法人向け電力プランページ」より、気軽にお問い合わせいただきたい。
<そのほかの関連記事>
非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説
【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説
【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?
【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?