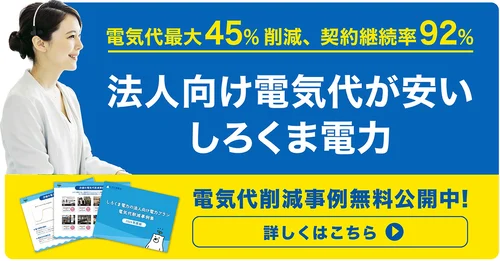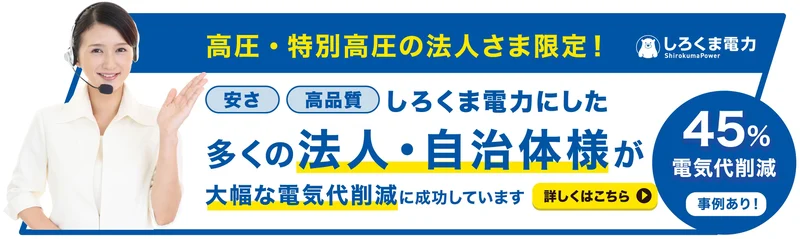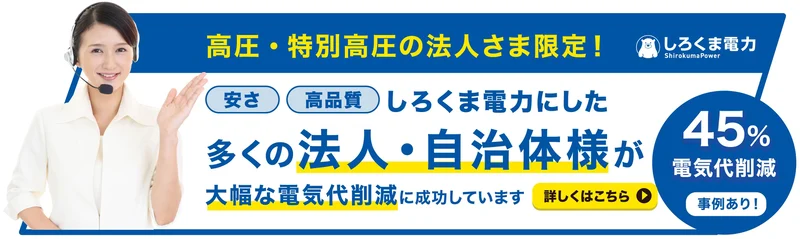特別高圧とは、法人を対象とした電力の契約形態のことだ。法人によって、電力の契約形態は、低圧・高圧・特別高圧と異なる。
【法人向け】動力とは?電気料金の仕組みや電灯との違いをわかりやすく解説!
.jpg?width=650&height=432&name=23555275_m%20(1).jpg)
動力は、大型機器を動かすためのエネルギーのこと。一般家庭では基本的に電灯契約のみだが、工場や店舗、オフィスビルなどでは動力契約を結んでいることが多い。とはいえ、動力の定義や電灯との違い、電気料金の仕組みの理解は難しいのではないだろうか。
この記事では、動力の定義や電気料金の仕組み、動力契約のメリット・デメリット、そして電気代を節約する仕組みまで網羅的に解説していく。
関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人ができる電気料金の高騰対策を解説!
関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法を徹底解説!
|
この記事を読んでわかること
|
動力とは?定義をわかりやすく解説
|
結論をまとめると
|
動力とは、業務用・産業用の機械設備を動かすために必要なエネルギーのことである。一般家庭で使われる「電灯」とは異なり、動力は業務用エアコンや業務用冷蔵庫、モーターを搭載した製造機械など、大きな消費電力を必要とする機器に使われることが特徴だ。
工場や店舗、オフィスビルなどで使用される大型機器は、一般家庭で使われる電力では稼働が難しい。そのため、より高い電圧で安定して電力を供給できる「動力契約」にすることで、効率的かつ安全に大規模設備を稼働できるのだ。
関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を解説!電気代を削減しよう
関連記事:電気代の高騰を解説!現状と推移、高い理由、今後の見通し、電気料金を安くする方法とは?
動力契約の電気料金の仕組み
|
結論をまとめると
|
動力契約の電気料金は、「基本料金」と「電力量料金」に加え、燃料価格の変動に応じて増減する調整額「燃料費調整額」と再エネ普及のために全国一律で支払う負担金「再生可能エネルギー発電促進賦課金」で構成される。
電気代の計算方法は以下だ。
| 電気料金 = 基本料金 +(電力量単価 ± 燃料費調整単価 + 再エネ賦課金)× 電力使用量 |
ここからは、4つの料金の中で決定方法が異なる基本料金と、理解しておきたい電力量料金について詳しく説明していく。
関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!
関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説
動力契約の基本料金とは
基本料金とは、契約電力(kW)に応じて発生する料金のこと。電気を使っていなくても支払う必要がある。
基本料金は、事前に契約した電力容量(kW)に応じて決定されるが、契約電力が10kW以下の場合は「契約電力制」、契約電力が10kW以上の場合は「最大需要電力制」に則って決定する。
契約電力制の場合、契約時に申請した電力(kW)を基準に基本料金が計算される。基本料金の例として、東京電力で20kWの契約を結んでいるケースを挙げてみよう。
| 20kW(電力容量)×1,098.05円(1kWあたりの基本料金)=21,961円 |
一方、最大需要電力制は、「過去1年間で最も使用電力が多かった30分間の平均使用電力(kW)」をもとに基本料金が計算される。例えば、最大需要電力が12kWの場合は以下の料金になる。
| 12kW(最大需要電力)×1,098.05円(1kWあたりの基本料金)=13,176.6円 |
動力契約においては、基本料金が電気料金全体に占める割合が高くなる傾向がある。特に、契約電力が10kWを超えて最大需要電力制が適用されている場合、一時的な電力使用のピークによって1年間の基本料金が大幅に増える可能性も避けられない。
一方で、動力契約は電力量料金が比較的安定していて低価格であるため、大量に電気を使う事業者にとっては長期的にはコストを抑えやすい契約形態でもある。
関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説
動力契約の電力量料金とは
次に、電力量料金とは、実際に使用した電力量(kWh)に応じて支払う変動料金である。
月々の電気使用量が多ければ多いほど、電力量料金も比例して高くなる仕組みだ。しかし、前述の通り、使用量は1kWhあたりの単価が一定で設定されているため、一般家庭などの電気料金のよりも安く抑えられることが多い。
電力量料金の特徴は、単価が夏季とその他の季節で分かれていることだ。東京電力の1kWあたりの電力量料金は、夏季で27.14円、その他の季節は25.57円となる。それぞれの季節に500kWh使ったと仮定した電気料金は以下の通りである。
|
夏季:500kWh(電力使用量)×27.14円(1kWあたりの基本料金)=13,570円
その他の季節:500kWh(電力使用量)×25.57円(1kWあたりの基本料金)=12,785円
|
しかし、前述の通り、使用量は1kWhあたりの単価が一定で設定されているため、一般家庭などの電気料金よりも安く抑えられることが多い。
関連記事:【最新】東京電力の電気料金値上げをわかりやすく解説!市場価格調整項とは?
関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!
燃料費調整額とは
燃料費調整額とは、燃料費の変動分を毎月の電気代に反映させたものである。各電力会社ごとに「基準」を設け、過去数ヶ月の平均額がその基準を上回った場合は電気代にプラスされ、基準より下回る場合は燃料費調整額もマイナスになる。
燃料費計算額の計算方法は以下のとおりである。
| 燃料費調整額(円)= 燃料費調整単価(円/kWh)× 電力使用量(kWh) |
なお、燃料費調整単価は燃料費の変動に合わせて1ヶ月ごとに変動する。
関連記事:電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説
関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説
再エネ賦課金とは
再エネ賦課金(さいえねかふきん)とは、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略称で、太陽光発電や風力発電など「再生可能エネルギー」の買い取りにかかった費用を電気代に反映したものを指す。
再エネ賦課金の計算式は以下の通りだ。
| 再エネ賦課金=再エネ賦課金単価(円/kWh)× 電力使用量(kWh) |
再エネ賦課金の単価は国が決めており、再エネの買取量に応じて一年ごとに見直される。個人・法人問わず、電力会社から電気を買う場合は支払わなければいけない。単価については全ての電力会社で同じである。
関連記事:【法人向け】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!
関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
動力と電灯との違いとは
|
結論をまとめると 動力と電灯との違いは以下の5つ ①供給される電圧 |
動力と似たものに「電灯」がある。電力会社の契約プランの種類が異なり、エネルギーの大きさが異なることがポイントだ。電灯の定義を簡単にまとめると、家庭や事務所で使うようなテレビ・パソコン・家電製品などを動かす電気のことである。
ここからは、動力と電灯との違いを詳しく見ていこう。
関連記事:デマンドレスポンスとは?仕組みやメリット、参加方法をわかりやすく解説!
関連記事:高圧電力とは?低圧や特別高圧との違い、契約の注意点もわかりやすく解説!
①供給される電圧
動力では主に200Vの電圧が供給される。200Vの電圧は、電灯で供給される100Vと比較して大きな電力を供給できるため、業務用エアコンや業務用冷蔵庫などの大型機器をスムーズに動かすことが可能だ。
また、電圧が高ければ高いほど、同じ電力を送るのに必要な電流が少なくなることで配線が発熱しにくくなる。使用電力量のロスを抑えられるだけでなく、発熱による電気火災の危険性も低く安全に使用できるため、大型機器には動力を使用しなければならないのだ。
関連記事:【最新】商業施設の節電方法をわかりやすく解説!法人におすすめの電気代削減方法とは?
②電気を送る方式(単相と三相)
電灯は「単相交流」、動力は「三相交流」といった電気を送る方式も違いのひとつである。
(出典:電気事業連合会「電気のいろいろ」)
三相交流の特徴は、3本の線によって電力を連続的かつ均等に供給できること。大きなエネルギーを必要とする機器を使う場合、2本の線と少ない配線の単相交流では効率的に稼働できない。
一方、三相交流は配線数が3本と多いため、大型機器の稼働も効率的におこなえる。そのため、多くの電気を使う店舗・工場などは動力を活用しているのだ。
また、三相交流の特徴として、大きな電気を送ることによるダメージの影響を受けづらいことも挙げられる。2本より3本の配線の三相交流のほうがダメージを受けづらく、機械の長寿命化が実現できるため、店舗・工場などには動力が欠かせないのだ。
関連記事:【図解つき】太陽光発電の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説!
関連記事:オフサイトPPAとは?オンサイトPPA・自己託送との違いをわかりやすく解説
③用途・利用する機器
以下の図は、動力と電灯それぞれの用途と利用機器の違いを示したものである。
|
用途
|
利用する機器
|
|
|
動力
|
業務・産業用
|
業務用エアコンや業務用冷蔵庫、
モーター、製造機械など
|
|
電灯
|
一般照明・小型家電
|
照明器具、テレビ、パソコン、
家庭用冷蔵庫など
|
ポイントは、業務で使うすべての機器が動力で用いるわけではないことだ。一般家庭でも使えるようなパソコンであれば通常の電灯で使用できる。しかし、天井に埋め込まれたエアコンや工場の機械などは非常に大きなエネルギーが必要なため、動力を使用しなければならない。
関連記事:【図解】太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
関連記事:自家消費型太陽光発電とは?導入するメリットやデメリットをわかりやすく解説
④コンセントの形状
動力用のコンセントは、一般的な家庭用コンセントとは異なり、差込口が複雑かつ大型で、主に3つ穴または4つ穴なことが多い。海外のコンセントに見られるような形状で、誤って家庭用機器を接続しないよう配慮された設計となっている。
一般家庭のコンセントで使える電化製品は「電灯」、使えない電化製品は「動力」が必要だと考えよう。
関連記事:省エネ法とは?2023年改正のポイントと概要をわかりやすく解説
関連記事:【法人向け】ソーラーカーポートとは?メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説
⑤電気代の決定方法
動力契約では、電力量料金が一律単価で設定されている。一方、電灯契約では電力量が三段階に分かれており、使用量が増えるにつれて1kWhあたりの単価も高くなる。
したがって、電力使用量が多い場合には、値段に変動のない動力契約のほうがコストを抑えやすい。例として、350kWhを使った場合の東京電力の電気代を挙げてみよう。
東京電力の電灯契約の場合、
|
で、合計すると12,152.5円の電気代が必要だ。その一方で東京電力の動力契約の場合、
|
夏季:350kWh(電力使用量)×27.14円(1kWあたりの基本料金)=9,499円
その他の季節:350kWh(電力使用量)×25.57円(1kWあたりの基本料金)=8,949円
|
と、電灯契約と電気代を比較すると、低価格になりやすい、ということがわかる。ただし、基本料金は契約電力によって決定するため、契約電力が大きいほど基本料金が高くなることには注意が必要だ。
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!
動力と電灯の違いをまとめると
動力と電灯の違いはわかっていただけただろうか。以下は動力と電灯の違いを簡単にまとめたものである。
| 動力 | 電灯 | |
| 供給される電圧 | 200V | 100V |
| 電気を送る方式 | 三相交流 | 単相交流 |
| 用途・利用する機器 | 業務用エアコン・大型冷蔵庫・製造機械など | 照明器具、テレビ、パソコンなど |
| コンセントの形状 | 海外コンセントのような複雑な形状 | 縦長の2つの差し込み口 |
| 電気代の決定方法 | 契約電力に応じた基本料金+一律の電力量料金 | 契約電力に応じた基本料金+使用量に応じた電力量料金 |
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説
動力を契約するメリット・効果
|
結論をまとめると 動力を契約するメリット・効果は以下の3つ ①電灯契約より従量料金が安くなる可能性がある |
業務用エアコン・大型冷蔵庫・製造機械など、動力機器に分類されるものを使用する場合は、動力契約が原則義務である。義務化されているのは、電気の仕様上、安全・安定した供給を確保するためだ。
では、動力を契約するメリット・効果はどのようなものだろうか。ここでは、3つのメリットを解説する。
関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説
関連記事:RE100とは?仕組みや日本の加盟企業についてわかりやすく解説
①電灯契約より従量料金が安くなる可能性がある
動力契約は、大量の電力を安定的に使う事業者向けに設計されており、電灯契約よりも1kWhあたりの単価が安く設定されていることが多い。
東京電力を例に挙げると、電灯契約の電力量料金は29.8円~40.49円かかるのに対し、動力契約は25.57円または27.14円に抑えることが可能だ。そのため、電灯契約より従量料金が安くなる可能性が高い。
一方で、電力会社からまとまった電気を一括で受け取る「高圧電力」は、動力契約より安価であることが多い。6,600Vの電圧が必要な工場・大型商業施設・病院で、50kW以上の契約を結ぶ場合は、動力より高圧電力を選ぶのが賢明だろう。
関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!
関連記事:【法人向け】電気代の削減方法を徹底解説!電気料金を安くしたい企業がすべき対策とは
②強い電力が安定的に使える
200Vの電圧を供給する動力は、大きなエネルギーを必要とする機器を長時間安定して稼働できる。設備の停止や電力不足によるトラブルを避けられることは、大きなメリットだろう。
例えば、製造ラインでの連続稼働や大型の空調システムなどを使う場合、電力が不安定だと品質・安全性に悪い影響を及ぼす可能性がある。動力契約を結んでいれば、そのような事態に陥ることなく、必要な電力を安定して受けられる環境の整備が可能だ。
業務を中断することがないため、効率性・生産性の維持も実現できるのだろう。
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
③モーターの効率がいい
動力における電気を送る方式・三相交流は、モーターの回転をより効率的かつ安定的におこなう電力の方式である。モーターの始動時の電流負荷が軽減され、スムーズな立ち上がりが実現するほか、運転中のトルク※も一定であるため、性能が安定しやすいことが特徴だ。
結果、故障リスクの低減やメンテナンス頻度の削減が見込まれ、設備の長寿命化や省エネルギー化にもつながる可能性も高い。
※トルク:回転させる力の強さ。トルクが安定するとモーターがスムーズかつ効率的に回転する。
関連記事:コーポレートPPAとは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説
動力を契約するデメリット・注意点
|
結論をまとめると 動力を契約するデメリット・注意点は以下の3つ①基本料金が高くなる可能性がある ②機器の設備工事が必要になる場合がある ③やめる場合に手続きが必要 |
動力機器を使用する場合は、動力契約を結ぶことが義務化されているが、確認しておきたい注意点がある。ここでは、3つのデメリット・注意点をわかりやすく解説する。
関連記事:【法人向け】太陽光発電のメリットとデメリットをわかりやすく解説!
関連記事:BCP対策とは?目的や策定方法・運用のポイントをわかりやすく解説!
①基本料金が高くなる可能性がある
動力契約の料金は、使用量に応じた電力量料金のほかに、契約電力制または最大需要電力制に応じた基本料金が加算される体系である。
特に、契約電力が10kW以上で適用される最大需要電力制は、1年でもっとも電力使用量が多かった30分間をもとに基本料金が算定されるため注意が必要となる。ある月に一時的に多くの機械を同時に動かしただけでも、その瞬間の使用量が記録され、年間を通して高い基本料金に影響することがあるからだ。
そのため、設備の稼働が一時的に集中しやすい業種や、繁忙期に大量電力を使用する事業者は、使用電力のコントロールなどの対策を講じないと、実際の利用量以上にコストが膨らむリスクがある。
関連記事:オンサイトPPAとは?オフサイトPPAとの違い、メリットデメリットをわかりやすく解説
②機器の設備工事が必要になる場合がある
動力を利用するには、200Vの三相電力に対応した設備やコンセント、大型の動力機器に電力を供給するための工事が必要である。新たに大型の動力機器を導入する場合は、設備工事が必須だ。
特に、テナントビルや築年数の古い物件では、動力の引き込み自体がされていないケースもある。動力引き込み工事からスタートする場合には工事費などを考慮し、コストに見合うものかの判断が重要だ。費用や工期の見積もりを事前に確認して、動力契約進めるといいだろう。
関連記事:太陽光発電の自己託送とは?仕組みやメリットなどをわかりやすく解説
③やめる場合に手続きが必要
使わなくなった機器がある場合、電力会社と手続きをしなければ、例え機器を使わなくても毎月料金が請求され続ける。
このため、工場の閉鎖や機器の撤去、移転などに伴って動力を使わなくなった際には、必ず契約先の電力会社に解約手続きを申し出なければならない。うっかり放置していると、何か月分も無駄な基本料金を支払うことになるため、注意が必要だ。
関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!
動力契約の電気料金を削減する方法
|
結論をまとめると 動力契約の電気料金の削減には、「電力会社の切り替え」で単価を下げることが効果的 |
動力契約の電気料金を削減するには、単純な節電ではなく、単価を下げることが効果的である。単価を下げる方法としてもっとも現実的なのが、「電力会社の切り替え」だ。
さらに今は法人向けの電力プランも数が増えている。例えば、
|
オフィスや工場など昼間の電力使用量が多い法人は「市場連動型プラン」
|
このように、自社に合わせた電力プランを選ぶことで、電気代削減効果を高られるのに加え、電気代の管理なども容易になる可能性がある。
どうしても「大手電力会社=安心」「新電力=不安」というイメージがあるかもしれないが、新電力の中にも倒産リスクがない法人は非常にたくさん存在する。
格安simのように、電力会社を切り替えても「電気の質」「停電リスク」は変わらないため、法人は一度、新電力に見積もりをとり、どれくらい電気代が安くなるかを確認してみるといいだろう。
電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、工数を減らすためにも、こうしたサービスを活用するといいだろう。
関連記事:【最新】法人の電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も> 御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう
しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。
電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。
以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。
しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。
また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。
見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。
見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、以下のページより、ぜひ気軽にお問い合わせいただきたい。