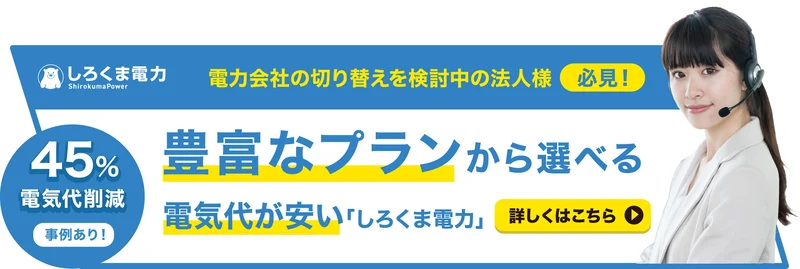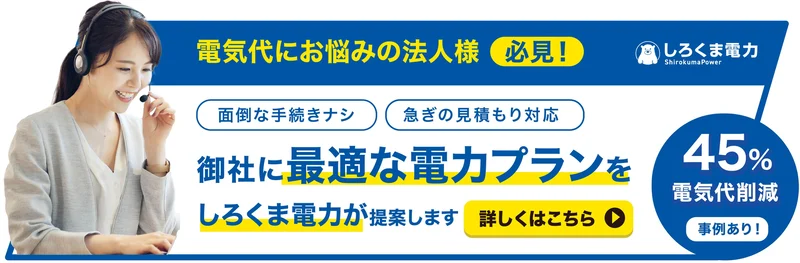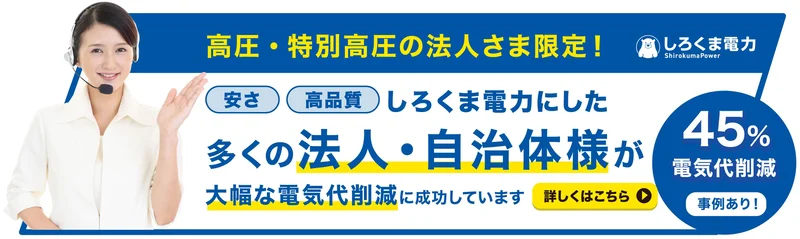法人向け電気代の内訳と計算方法をわかりやすく解説!電気料金の削減方法も紹介

※この記事は2025年4月24日に最新の情報に更新されました。
電気代の値上げが続いている。しかし電気料金を安くするために節電しても、思ったよりも電気代が下がらなかった、という法人も多いのではないだろうか。
会社の電気代を下げるにあたり、知っておきたいのが「電気代の内訳と計算方法」だ。電気代はいくつかの要素から成り立っているため、それらを理解し、適切な対策を講じることで電気代を安くできる。
そこでこの記事では、法人に対し、電気代の内訳と計算方法を紹介。それぞれの要素を説明したあと、電気代を安くする方法を紹介する。
|
この記事でわかること ・法人の電気代はどのような要素で成り立っているのか ・法人の電気代はどうやって計算するのか ・法人の電気代はどうすれば削減できるのか |
関連記事:電気代値上げを徹底解説!推移と料金が高い原因、今後の見通し、法人ができる高騰対策とは
関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人ができる電気代削減術を解説!
|
目次 法人の電気代の内訳とは?それぞれの要素を解説 法人が月々の電気料金を安くする方法とは? |
法人の電気代の内訳と計算方法
|
結論をまとめると ・電気代は4つの内訳をもとに成り立っている。 ・内訳ごとに対策を講じることで法人の電気代を安くできる。 |
最初に法人の電気代の内訳と計算方法を見ていく。ほとんどの電力会社の場合、法人向け電気代の内訳は以下のようになっている。

このように、電気代は4つの要素から成り立っている場合がほとんどだ。法人の電気代の計算方法は以下である。
| 法人の電気代 = 基本料金 +(電力量料金単価 ± 燃料費調整単価 + 再エネ賦課金)× 電力使用量 |
法人の電気代は、定額の「基本料金」があり、そこに電力使用量に応じた「電力量料金単価」「燃料費調整単価」「再エネ賦課金」が加わることで計算できる。
これらの内訳ごとに対策を講じることで、電気代は効率よく削減することができるのだ。
関連記事:【最新】法人の電気代が高いのはなぜ?電気料金が高騰する理由と対策をわかりやすく解説!
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
法人の電気代の内訳とは?それぞれの要素を解説
|
結論をまとめると ・再エネ賦課金の単価は全社共通だが、それ以外の単価は電力会社ごとに異なる。 |
電気代には4つの要素があることを解説してきた。次に、電気代のそれぞれの内訳について詳しく見ていく。
関連記事:電気代の補助金制度をわかりやすく解説!いつまで?補助内容をわかりやすく解説!
関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
基本料金とは?
基本料金とは、電気の使用量に関係なく毎月定額で発生する料金のことだ。基本料金は発電設備の維持費用や人件費、機材費などを賄うために設定されており、一年ごとに見直される。基本料金の計算方法は以下だ。
| 法人の電気代の基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力 ×(185 − 力率)÷ 100 |
基本料金の単価は電力会社ごとに異なるもので、そこに契約電力と力率をかけた上で基本料金が決定する。
力率とは「電力会社から届いた電力をどれだけ効率よく使用できたか」を示す割合のことだ。設備が新しい工場などは力率が高く、設備が古い工場などは余分なエネルギーを消費するため力率が低くなりやすい。
法人の場合、力率が85%以下なら基本料金が割高になり、85%以上の場合は安くなるため、電気料金の明細書で自社の力率を確認することをおすすめする。
そして契約電力とは「1年間でどれくらい電気を使う可能性があるのか」を予測した数字のことだ。契約電力の決定方法は、法人の規模によって「実量制」と「協議制」の2種類にわかれる。
関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説
契約電力の実量制とは?
実量制とは、過去1年間の電力使用量のうち、最も電気を多く使った30分間の電力使用量(デマンド値という)を契約電力とすることだ。実量制の対象となるのは、「低圧電力」または契約電力が50〜500kWの「高圧電力の小口」である。
実量制で契約電力が決まる流れは以下だ。
|
①過去1年の「30分ごとの電力使用量」を出し、月ごとに最大値をまとめる。
②各月ごとに出した「30分ごとの最大電力使用量」を比較する。
③最も大きい電力使用量が契約電力となる。
|
わかりづらいかと思うので、具体例を出して簡単に解説する。
上図は法人の年間の最大需要電力を図にしたものだ。この場合、30分ごとの電力使用量が最も大きいのは8月である。そのため、8月の最大需要電力が契約電力となる。
契約電力の協議制とは?
協議制とは、年間のデマンド値などをもとに、電力会社と協議を行ったうえで基本料金を決める方法だ。
協議制の対象となるのは、契約電力が500〜2,000kWの「高圧大口」、2,000kW以上の「特別高圧」の法人である。
これらの法人は電力使用量が多いため、もし停電や事故が発生した場合に広範囲で停電が発生するなど、周囲に与える影響が大きくなってしまう。
そのため協議制では、過去の電力使用量や設備の使用、今後の稼働計画などをもとに電力会社と話し合った上で基本料金が決定される(年に1回、見直しが実施される)。
電力量料金とは?
電力量料金(従量料金)とは、使用した電力量に応じて請求される料金のことだ。
電力会社ごとに1kWhあたりの単価が設定されており、電力使用量をかけることで算出できる。
電力量料金の単価は、図のように3段階に分かれている場合が多い。これを三段階料金といい、電気を使用する量が増えるほど単価も上がっていく仕組みだ。
また電力会社によっては季節や時間帯によって異なる単価が設定されていたり、単価が固定だったりとさまざまなプランがある。
燃料費調整額とは?
 燃料費調整額とは、火力発電で使用する石油や石炭、天然ガスなどの「化石燃料」の価格変動分を電気代に組み込んだものだ。
燃料費調整額とは、火力発電で使用する石油や石炭、天然ガスなどの「化石燃料」の価格変動分を電気代に組み込んだものだ。
こちらも電力量料金と同じく、燃料費調整単価に電力使用量をかけることで計算できる。
ちなみに燃料費は世界情勢や為替レートでこまめに変動するため、燃料費調整単価も過去数ヶ月間の燃料費をもとに毎月変動する。
もし燃料費が平均よりも高い場合は電気代に単価が上乗せされ、安い場合はそれだけ割引される仕組みだ。2022年に電気代が過去最高値となったが、高騰の原因はこの燃料費調整額である。
また新電力の中には、燃料費でなく「JEPXの市場価格(電気の卸市場の取引価格)の変動分」を電気代に落とし込む場合もある。この場合の料金内訳を、市場価格調整単価や電源調達調整費、独自燃調などという。
関連記事:【図解】電気代を左右する燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通しをわかりやすく解説
関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説
関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説
再エネ賦課金とは?(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
 再エネ賦課金とは、太陽光発電や風力発電など「再生可能エネルギー」の買い取りにかかった費用を電気代に反映したものである。
再エネ賦課金とは、太陽光発電や風力発電など「再生可能エネルギー」の買い取りにかかった費用を電気代に反映したものである。
国はカーボンニュートラルの実現に向けて国内に再エネを増やすために、「FIT制度(固定価格買取制度、2012年開始)」や「FIP制度(固定価格差補助金制度、2021年開始)」を通して発電事業者から再エネでできた電気を買い取っている。
投資的側面を持たせることで日本の再エネ導入量は増えているが、この再エネの買取にかかった費用を、私たちは再エネ賦課金という形で負担しているのだ。
再エネ賦課金は家庭や法人に関係なく支払う義務がある。また単価は年度ごとの再エネ導入量をもとに国が決めるため、どの電力会社でも同じだ。
関連記事:電気代の再エネ賦課金とは?仕組みと推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!
関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!
法人が月々の電気料金を安くする方法とは?
|
結論をまとめると ①最大電力使用量(最大デマンド値)を下げる |
ここまで法人の電気代の内訳について解説してきた。最後に、法人ができる電気代削減方法を紹介する。
①最大電力使用量(最大デマンド値)を下げる
 1つ目が基本料金を安くする方法だ。
1つ目が基本料金を安くする方法だ。
先述したように、基本料金は主に「最大電力使用量(最大デマンド値)」をもとに決まるため、30分間の電力使用量を減らすことで単価を下げることができる。
デマンド値を下げる方法として考えられるのが、エネルギーマネジメントシステム(EMS)またはデマンドコントローラー(デマコン)の導入だ。
EMSとは、エネルギー(電気・ガス・水道)の使用状況を見える化し、管理や分析、制御を行うシステムのことである。BEMS(ビルや商業施設向け)やFEMS(工場向け)、CEMS(地域全体を管理できる)など様々なシステムがある。
一方、デマンドコントローラーとは、電力使用量を見える化できる装置のことだ。上限を設定すれば、超えないように設備を自動制御してくれる。デマコンは主に空調や照明の管理を行うものだが、工場の生産設備に設置できる場合もある。EMSよりもデマコンの方が安価で、申し込みから1ヶ月程度で設置できるケースが多い。
こういったシステムや装置を導入すれば、最大電力使用量(最大デマンド値)を下げて基本料金を安くできる。
②節電を徹底する
2つ目の方法が節電の実施だ。電気代の単価自体が上がる今、電気の使用量を減らすことで電気代を安くすることができる。例えば照明をLEDにすれば、消費電力を蛍光灯の約50%、白熱電球の約80%削減できるのだ。
しかし節電といっても、具体的にどこをどうすればどれだけの効果が得られるのかは非常にわかりづらい。そこで下記記事で、オフィスと工場ですぐにできる節電方法と、それぞれの取り組みで得られる節電効果を解説した。ぜひご確認いただきたい。
関連記事:【最新】オフィスですぐできる節電方法を21つ解説!電気代を削減しよう
関連記事:【最新】工場の節電・電気代削減に効果的な方法16つを徹底解説!
③電気代の単価が安い電力会社にする
3つ目の方法が電力会社の切り替えだ。節電に加えて、今よりも単価の安い電力会社と契約することで、電気代をさらに安くできる。
2025年現在、大手電力をはじめ多くの電力会社が値上げに踏み切っている。しかし新電力(2016年以降に新規参入した電力会社)によっては、現在の契約先よりも電気代を安くできる可能性があるのだ。
「節電をしても電気代が安くならない」「使用量を気にせず電気を使いたい」場合は、電力会社の切り替えを検討するといいだろう。
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みと2022年に契約するメリット・デメリットを解説!
関連記事:電気代を安くしたい法人必見!電力会社の選び方を徹底解説!
関連記事:電力会社の乗り換えで法人の電気代は安くなる?切り替え方とメリット・注意点を解説
④自社に合った電力プランに切り替える
4つ目の方法が、自社に合った電力プランに切り替え、電気代のコストパフォーマンスを高めることだ。
電気代の単価が安い会社にするのはもちろんだが、それに加えて「自社に合った電力プラン」を選ぶことで、電気代をさらに安くすることができる。
例えば、
|
など、法人によって選ぶべき電力プランは異なるのである。
現在、大手電力あるいは新電力が提供する「法人向け電力プラン」を契約中の法人が多いのではないだろうか。実はこのプラン、法人によって多少単価に違いがあるものの、基本的にはどの法人に対しても電気代の仕組みは同じである。
「大手電力=安心」というイメージがあったり、現状から電力プランを見直すのは怖い、と感じるかもしれない。だがこれからは「自社にあった電力プランを選んで効率よく電気代を下げていく」取り組みが非常に重要なのである。
電力会社によっては「プランを会社ごとにカスタマイズできる」「適切な電力プランを提案してくれる」会社もあるため、電力会社選びが面倒な場合は、こうした法人から見積もりをとるのも一つの手だろう。
関連記事:【図解】法人向け市場連動型プランとは?従来メニューとの違い、メリットとデメリットを徹底解説
関連記事:電力の最終保障供給とは?2022年9月から大幅値上げ!制度の概要と高騰対策を解説!
<業界トップクラスのプラン数!電気代を45%削減した例も>
御社に最適なプランで電気代・CO2を削減しよう
しろくま電力では、高圧・特別高圧の電力を使用する法人向けに電力プランを提供している。
しろくま電力の強みは「電気代の安さ」と「業界トップクラスのプラン数」だ。

電気代が大手電力より安いのはもちろん、「電気代をとにかく安くしたいから市場連動型プラン」「価格の安定性も重視したいから燃調リンクプラン」など、ニーズに合わせて電力プランを選ぶことができる。中には電気代を45%(1.5億円)削減したプランもある。プランをカスタマイズし、御社だけの電力プランを作ることも可能だ。
以下はしろくま電力を導入する主な企業・自治体である。

しろくま電力は、入札制(価格が安い場合に導入が決まる)を実施する数多くの自治体に対しても電力供給を行っている。多くの法人からも低価格であることが好評で、契約更新率は92%を超えた。
また、しろくま電力の電気は全てCO2を一切排出しない実質再生可能エネルギーだ。電気を切り替えるだけで御社のCO2削減量を減らすことができる。
見積もりは「複数のプランの電気代の提示」や「現在の契約先との電気代・CO2削減量の比較」にも対応している。「どれがいいかわからない」法人にはこちらからプランを提案することも可能だ。
見積もりだけでなく「プランについて説明してほしい」「なぜ安いのか、本当に倒産しないか知りたい」といった面談も行っている。切り替えを検討中でなくとも、気軽にお問い合わせいただきたい。
関連記事:【最新】スーパーマーケットの節電方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気代削減方法とは?
関連記事:【最新】病院の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき対策とは?
関連記事:【最新】パチンコ店の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!法人がすべき電気料金対策とは?
関連記事:【最新】宿泊施設(ホテル・旅館)の節電・電気代削減方法をわかりやすく解説!事例も紹介
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説
関連記事:最終保障供給とは?制度の仕組みや料金内容、注意点をわかりやすく解説!
関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!