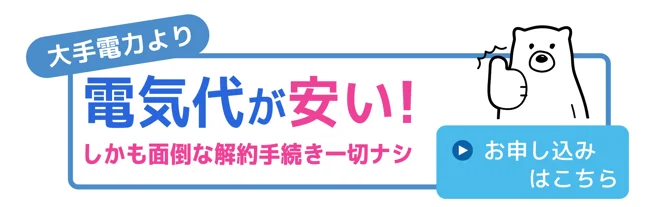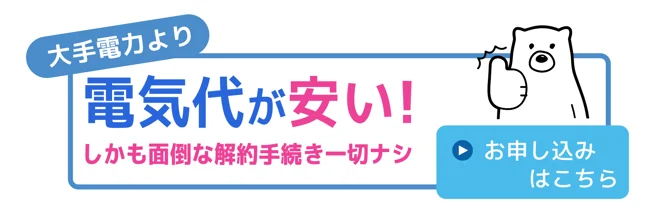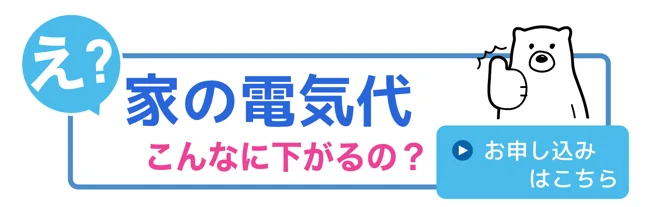暑い季節になると大活躍する冷房。しかしエアコンを頻繁に使っていると電気代が気になりますよね。この記事に辿り着いた方の中には
【2026年最新】電気代・ガス代の補助金制度をわかりやすく解説!いくら値引きされる?

※この記事は2025年7月22日に最新の情報に更新されました。
2025年7月から9月まで、電気代・ガス代の補助金制度である「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が再開されることになりました。
この記事では、具体的な値引き金額や制度が実施される背景などを解説し、今後も電気代の補助金は続くのか、補助金なしでも電気代を安くできる方法はあるのか、わかりやすく説明していきます。
|
この記事を読んでわかること ・電気代とガス代の補助金制度ってなに?いくら値引きされるの? ・なぜ補助金制度が実施されているの?支援は今後も継続されるの? |
関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
関連記事:【最新】世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説
【2025年1月から復活】電気代・ガス代の補助金制度とは?
|
結論をまとめると ・政府は過去数回にわたって家庭と一部法人の電気代を値引きしている。 ・補助金だがお金は支給されない。値引きされた金額が請求される。 |
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」とは、政府が実施する電気代・ガス代の補助金制度のことです。
政府はこれまでも、以下のように家庭や一部法人の電気代とガス代を補助していました。
|
その後について「補助金は再開されないのでは」という見方が多かったのですが、物価高が続いていることから、政府は2025年4月22日に改めて電気代・ガス代の補助金制度の再開を決定。2025年7月から9月まで「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が再開されることになりました。
電気代・ガス代の補助対象は?お金は直接支給される?
「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の対象となるのは、一般家庭や小規模商店(低圧)または法人(高圧)です。電力契約が特別高圧、あるいはガスの年間契約量が1,000万㎥以上の法人は対象ではありません。
上図は電気代・ガス代の補助金のスキームを図にしたものです。ここで注意しておきたいのは、電気代・ガス代の補助金は電力需要家に直接支給されるわけではない、ということです。
政府が補助金を交付するのは「政府に申請を行った全ての電力会社(ガス会社)」で、家庭や法人に対しては補助金を差し引いた電気代・ガス代が請求されます。
特別な申請や手続きは不要ですが、契約中の電力会社(ガス会社)が申請していないと補助対象になりません。自分が対象か気になる方は、経済産業省の「採択された電気・都市ガスの小売事業者などの一覧」から会社を検索してみてください。
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
電気代・ガス代の値引き金額はいくら?
|
結論をまとめると ・家庭向けの電気代は、2025年7月と9月分は2.0円/kWh、8月分は2.4円/kWhが値引きされる。 ・法人向けの電気代は、2025年7月と9月分は1.0円/kWh、8月分は1.2円/kWhが割引される。 ・値引き金額に上限はない。電気を使った分だけ値引きは行われる。 |
ここまで電気代・ガス代の補助金制度の概要を解説しました。次に「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の補助金額を見ていきましょう。
| 電気代 | ガス代 | ||
| 一般家庭(低圧) | 法人(高圧のみ) | ||
| 2023年1月〜8月 | 7.0円/kWh | 3.5円/kWh | 30.0円/㎥ |
| 2023年9月〜2024年4月 | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 15.0円/㎥ |
| 2024年5月 | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh | 7.5円/㎥ |
| 2024年8月・9月 | 4.0円/kWh | 2.0円/kWh | 17.5円/㎥ |
| 2024年10月 | 2.5円/kWh | 1.3円/kWh | 10.0円/㎥ |
| 2025年1月・2月 | 2.5円/kWh | 1.3円/kWh | 10.0円/㎥ |
| 2025年3月 | 1.3円/kWh | 0.7円/kWh | 5.0円/㎥ |
| 2025年7月・9月 | 2.0円/kWh | 1.0円/kWh | 8.0円/㎥ |
| 2025年8月 | 2.4円/kWh | 1.2円/kWh | 10.0円/㎥ |
上図は電気代とガス代の値引き金額の推移を図にしたものです。
今回の補助金では、家庭向けの低圧電力は2025年7月・9月分は1kWhあたり2.0円、8月分は少し補助額が増えて1kWhあたり2.4円が値引きされます。法人向けの高圧電力の補助金額は、2025年7月・9月分は1kWhあたり1.0円、8月分は1kWhあたり1.2円です。
この補助金には上限がないため、電力使用量がいくら増えても必ず値引きされます。
関連記事:電子レンジの電気代はいくら?計算方法や6つの節約術をわかりやすく解説!他の電化製品とも徹底比較
関連記事:パソコンの電気代はいくら?デスクトップやノート、ゲーミングPCの消費電力と節約方法をご紹介
電気代の補助金で家庭の電気代はいくら安くなる?
|
結論をまとめると ・値引き金額は大きくて1,000円程度。 ・一人暮らしであまり電気を使わない場合、あまり電気代は安くならない。 |
ここまで電気代の補助金額について解説しましたが、これにより、家庭の電気代はどれくらい安くなるのでしょうか?
|
世帯
|
電気使用量
|
補助金額
(2025年7月・9月使用分) |
補助金額
(2025年8月使用分) |
|
一人暮らし
|
150〜250kWh
|
300〜500円
|
360〜600円 |
|
二人暮らし
|
250~350kWh
|
500〜700円 | 600〜840円 |
|
四人暮らし
|
400~500kWh
|
800〜1,000円 | 840〜1,200円 |
上図は補助金額を世帯人数別に図にしたものです。こうして見ると多くても月1,000円程度と、そこまで大きく電気代が安くなるわけではありません。しかし、それでも電気代がある程度は安くなることがわかります。
関連記事:一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!
関連記事:二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!
関連記事:4人家族の電気代平均はいくら?季節別や地域別の平均、料金が高い原因や節約方法をご紹介
電気代の補助金制度が実施される理由とは?
|
結論をまとめると ・電気代補助金の背景は燃料費高騰や物価高対策など、実施される時期によって異なる。 |
ここまで補助金制度の概要と補助金額を解説してきました。これまでに2回、電気代とガス代の補助金制度は実施されていますが、これは一体なぜなのでしょうか?
関連記事:【最新】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる高騰対策を解説!
関連記事:【最新】電気代が高いのはなぜ?電気料金を安くする方法を解説
①2025年に「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が実施される理由
2025年1月〜3月に「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が実施される理由は、先述したように物価高が続いていること、そして冬は電力やガスの使用量が増加するからです。
|
春(4〜6月)
|
夏(7〜9月)
|
秋(10〜12月)
|
冬(1〜3月)
|
|
|
単身世帯
|
5,486円
|
5,842円
|
5,833円
|
9,340円
|
|
2人世帯
|
10,091円
|
8,930円
|
9,163円
|
15,577円
|
|
3人世帯
|
12,058円
|
10,285円
|
10,543円
|
18,356円
|
|
4人世帯
|
12,561円
|
10,689円
|
10,936円
|
19,941円
|
|
5人世帯
|
13,130円
|
11,124円
|
11,476円
|
21,763円
|
|
6人以上世帯
|
15,351円
|
17,474円
|
15,671円
|
27,267円
|
(出典:e-Stat「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 」)
上図は、2023年度における季節ごとの電気代の平均額をまとめたものです。「冬にガスの使用量が増える」というのはイメージできるかもしれませんが、実は電気代も冬が高くなる傾向にあります。その一方、電気代が高いイメージがある夏はあまり高くありません。
これは冬は夏よりも室温と気温の差が大きくなるからです。冷房を使う場合よりも暖房の方が気温差が大きいため、その差を埋めようと多くの電気を使います。
冬は電気代が高くなることから、国民の負担を軽減するために2025年1月から3月まで「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が実施されることになりました。
②2023年に「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が実施された理由
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」は元々2023年1月〜2024年5月まで実施されていました。
この時期に補助金制度が実施された理由は、2022年に発生した「ロシア・ウクライナ問題」や「急激な円安の進行」などにより、化石燃料費(石油・石炭・天然ガス)が大幅に高騰したからです。
特にロシアは、天然ガスの生産量が世界1位、石油と石炭も世界トップ3に入るほどの資源大国です。このロシアに対し経済制裁を課したことで世界に出回る燃料が減り、燃料費が大幅に値上がりする事態となりました。

現在、日本の電気は約8割が火力発電で作られており、その際に使用する化石燃料(石油・天然ガス・石炭)の約9割が海外からの輸入によって賄われています。その燃料費が上図のように跳ね上がったことで電気代とガス代も一気に上昇。2022年には電気代が過去最高値となりました。
こうした事態を受けて「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が実施され、燃料費が落ち着き始めた頃を見計らい、この補助金制度は終了となっています。
③2024年に酷暑乗り切り緊急支援が実施された理由

2024年8月から10月まで、電気代とガス代の補助金である「酷暑乗り切り緊急支援」が実施されました。
この補助金制度が実施された理由は物価高対策です。物価上昇は年金で生活する高齢者や、経営が苦しい中小企業にとって死活問題であるため、緊急支援策として実施されることになりました。
「酷暑」という制度名にもあるように、今回の補助金は夏にフォーカスしたものであること、さらに実施が急に決まったために自民党内でさまざまな不満の声が上がっていることから11月で終了されています。
電気代・ガス代の補助金は今後も実施される?
先述しましたが、電気代・ガス代の補助金の実施期間は2025年7月〜9月の3ヶ月間です。補助金が電気代に反映されるのは、2025年8月〜10月の請求分となります。
それでは、2025年4月以降も電気代とガス代の補助金制度は実施されるのでしょうか?
関連記事:今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
今後も補助金制度が実施される可能性はある
断言はできないものの、今後も電気代とガス代の補助金制度が実施される可能性は考えられます。理由は依然として物価高が続いており、家計の負担が軽くなっているとは言い難いからです。
4月以降も補助金制度が延長されるかはわかりませんが、「酷暑乗り切り緊急支援」のように、今後も電力使用量が増加する夏や冬などに補助金制度が実施される可能性は十分に考えられます。
電気代の補助金で電気代は本当に安くなるのか?
それでは、今回の電気代支援で、家庭の電気代は安くなるのでしょうか?結論から言うと、補助金制度で電気代が安くなる可能性は限りなく低いと考えられます。特に大手電力会社は2023年6月に電気代を大幅に値上げしており、値引き金額よりも値上げ幅の方が大きいケースが多いのです。
| 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力EP | 北陸電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | |
| 値上げ率 | 約23% | 約26% | 約16% | 約40% | 約26% | 約29% | 約33% |
上図は各大手電力会社の家庭向け電気料金の値上げ幅です。各社の電気代の具体的な値上げ金額を見ると、例えば東電EPは電気代の単価を10円/kWh以上値上げしています。
電気代自体が大幅に上がっているため、今回の電気代の補助金は「電気代が安くなる」よりは「値上げの負担が軽減される」という方が近いでしょう。
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
節約したい方必見!電気代を安くする方法を5つ紹介
ここまで電気代の補助金について解説しました。2024年10月以降、補助金額がさらに下がることから、電気代が高くなる可能性が高いです。そこで最後に、家庭の電気代を安くする方法を5つ紹介します。
関連記事:【最新】無料で電気代を安くする方法を徹底解説!電気料金を安くしたい方必見!
電気代を安くする方法①:契約アンペア数を見直す
1つ目の方法が、契約アンペア数の見直しです。アンペア制を設けている電力会社の場合、契約容量を見直せば基本料金が下がり、電気代を安くできます。例えば東京電力で考えると、40Aから30Aにすれば月々の電気代が296.24円、20Aにすれば590.48円も安くなるのです。
ただし、契約アンペア数を低く設定しすぎると、ブレーカーが落ちやすくなってしまいます。変更後は1年間数字が変更できない電力会社も多いため、この点には注意しておきましょう。
上図は家電ごとの一般的なアンペア数です。同時に使用することの多い家電のアンペア数を把握した上で、最低限余裕のあるアンペア数へと変更することをおすすめします。例えば一番家電を使う際の合計アンペアが26Aの場合、30Aで契約すると停電の心配をせずに済みます。
関連記事:電気代の内訳の見方と計算方法とは?電気代を安くする方法もわかりやすく解説!
関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説
電気代を安くする方法②:支払い方法を口座振替にする
電気代を下げる2つ目の方法が、支払い方法の変更です。電力会社によっては、口座振替に変更することで電気代が年間数百円ほど安くなる場合があります。
ただし、電力会社によってはクレジットカードでしか支払えないケースもあるので注意しましょう。またポイント還元率によっては、クレジットカード支払いの方が節約につながる場合もあるため、どちらの方がお得なのか、まずは計算してみるといいでしょう。
電気代を安くする方法③:節電を徹底して行う
3つ目が節電の徹底です。使用電力の多い家電の使い方を見直し、消費電力量を減らせば、それだけ電気代を安くすることができるのです。ここからは、各家電の節電方法と、それによって得られる節電効果について説明していきます。
3つ目が節電の徹底です。先述したように電気代は使用量を減らすことで安くできます。ここからは特に使う機会が多い家電の節電方法と、期待できる節電効果を解説します。
|
エアコン(冷房・暖房)の
節電方法 |
・適温は、夏が28度で冬が20度
・夏の場合、冷房を1度あげる ⇨ 約13%の節電 ・冬の場合、暖房を1度下げる ⇨ 約10%の節電 ・月に一度のフィルター掃除 ⇨ 約50%の節電 |
|
冷蔵庫の節電方法
|
・冷蔵庫の開閉回数を減らす ⇨ 約12%の節電
・冷蔵庫の開閉時間を減らす ⇨ 約5%の節電
・冷蔵庫を壁から少し離す ⇨ 約5%の節電
・「冷蔵庫を壁から少し離す」「直射日光が当たらない場所に置く」「食品を冷ましてから入れる」「冷蔵庫内は7割程度しか詰めない」も効果的
|
|
照明機器の節電方法
|
・蛍光灯や白熱電球からLEDに変える ⇨ 約80%の節電
・こまめに電源をオフにする ⇨ 約5%の節電
|
|
テレビの節電方法
|
・つけっぱなしや「ながら見」をやめる ⇨ 約2%の節電
・「テレビの主電源をオフにする」「コンセントを抜く」のも効果的
|
|
洗濯機・洗濯乾燥機の節電方法
|
・すすぎを2回から1回に減らす ⇨ 約17.5%の節電
・「月に一度のフィルター掃除」も効果的
|
関連記事:エアコンの電気代はいくら?1時間ごとの計算方法や節約術をわかりやすく解説!つけっぱなしの方が安い?
関連記事:冷蔵庫の電気代はいくらくらい?9つの節約方法もあわせて解説!
関連記事:テレビは電気代が高い?種類ごとの電気代や節約方法をわかりやすく解説!
関連記事:洗濯機の電気代と水道代は1回いくら?6つの節約術も徹底解説!
関連記事:サーキュレーターと扇風機の違いとは?特徴や使い方、電気代の節約術をわかりやすく紹介!
関連記事:パソコンの電気代はいくら?デスクトップやノート、ゲーミングPCの消費電力と節約方法をご紹介
電気代を安くする方法④:省エネ家電に買い替える
電気代を下げる4つ目の方法が家電の買い替えです。環境省によると、電化製品は年々省エネ性能が上がっていることがわかっています。
例えば、2019年製の冷蔵庫は、2009年のものと比較すると年間消費電力量を約40〜47%もカットすることが可能です。エアコンはこの10年間で約17%も節電でき、テレビは約42%も節電できることがわかっています。
また、家電の買い替えはコストが発生しますが、東京都世田谷区や愛知県一宮市など自治体によっては省エネ家電の買替に活用できる補助金制度を実施しているケースもあります。
環境省の比較サイトでは、実際に家電を買い替えた場合にどれだけ電気代を安くできるのか、製品ごとに調べることができるため、買い替えを検討中の方はぜひご活用ください。
電気代を安くする方法⑤:電力会社を切り替える
5つ目の方法が電力会社の切り替えです。節電・省エネ家電の買い替えでも電気代削減効果は十分に期待できます。しかし電気代を安くするために最も効果的なのは「電気代の単価自体を下げる」取り組みです。
そして単価を下げる方法が、電力会社の切り替えです。先述したように、2023年6月より大手電力会社は大幅な電気料金の値上げに踏み切っています。
「大手電力会社=安心」というイメージがあるかもしれませんが、その神話は崩れつつあります。先述したように北陸地方は地域別で見ると電気代が最も高いため、特に注意が必要です。
一方、新電力(2016年以降に新規参入した電力会社)によっては、格安の電気プランを提供しているケースがあります。電気代が上がる現在でも、安くできる可能性はあるため、特に大手電力会社と契約中の方は、電力会社の切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事:【最新】電力会社の選び方とは?会社選びの注意点と電気代を安くする方法をわかりやすく解説!
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしませんか?
しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供しています。
このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。
 ※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、
※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、
しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。
また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。
環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みください。申込ページでは、プランの詳細についてわかりやすく説明しています。
またしろくま電力では、電気料金の高騰に悩む法人(高圧・特別高圧)に向けて、昼間の電気使用量が多いほどお得になる電力プランを提供しています。気になる方は、ぜひ「市場連動型しろくまプラン」をご覧ください。
※実質再生可能エネルギーとは、電気に環境価値証書(CO2を出さないという証明書)を組み合わせたもののこと。
<その他おすすめ記事>
関連記事:オール電化の電気代は高い?高い原因や平均額、節約術をわかりやすく解説
関連記事:ホットカーペットの電気代は高い?エアコンなどの暖房器具と比較して解説
関連記事:暖房の設定温度は何度が理想?冬に電気代を節約しつつ快適に過ごすコツとは?
関連記事:エアコンの暖房の電気代は高い?節約方法もあわせて解説!
関連記事:電気毛布の電気代はいくら?24時間つけっぱなしにすると高い?こたつやエアコンとも比較!
関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説
関連記事:オイルヒーターの電気代は高すぎる?他の暖房器具との比較や節約方法を解説!
関連記事:炊飯器の電気代はいくら?8つの節約方法もわかりやすく解説!