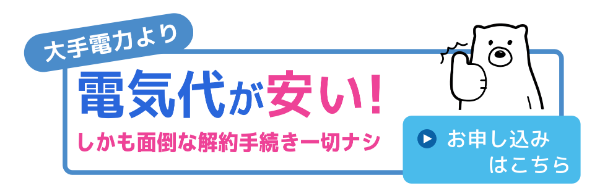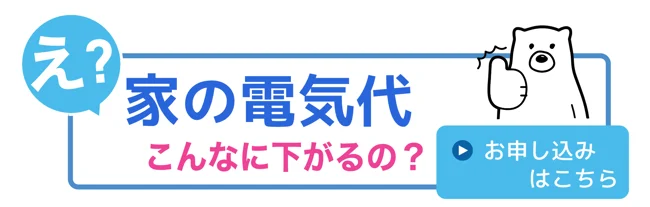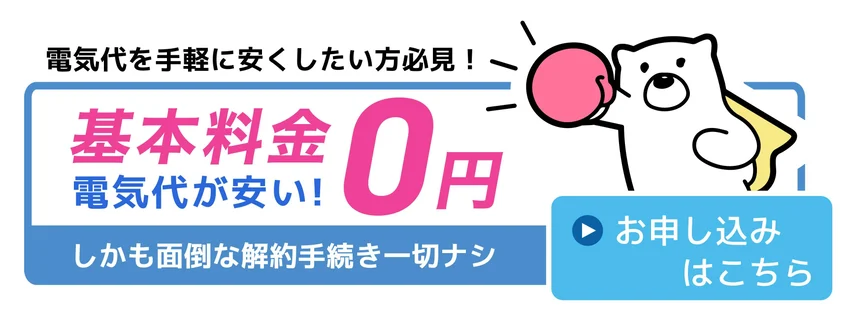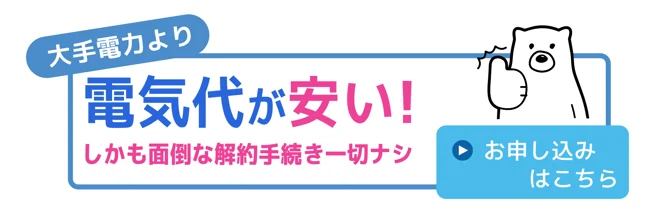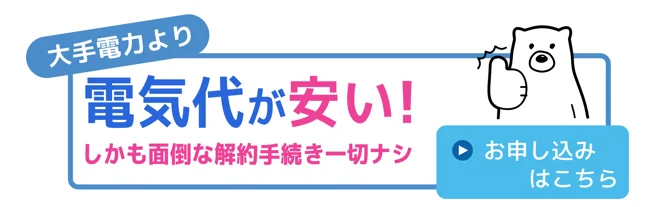サーキュレーターと扇風機の違いとは?特徴や使い方、電気代の節約術をわかりやすく紹介!

古くから親しまれる扇風機と、見た目がそっくりのサーキュレーター。どちらも風を起こすアイテムですが、実はそれぞれ違った特徴があることをご存知でしょうか。
「サーキュレーターと扇風機の違いって?」
「サーキュレーターと扇風機の効果的な使い方は?」
「サーキュレーター、扇風機の電気代を節約する方法とは?」
この記事では、上記のような疑問を解消すべく、サーキュレーター・扇風機の違いを解説。後半では、購入時に押さえておきたいポイントや、電気代の節約方法も紹介します。
関連記事:世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説
関連記事:【2025年最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
サーキュレーターと扇風機の違いとは?
サーキュレーターと扇風機の違いは「使用目的」にあります。下の表に、主な違いをまとめてみました。
| 目的 | 風の特徴 | 風量 | |
| サーキュレーター | 空気を循環させること | まっすぐ遠くまで届く | 強い |
| 扇風機 | 涼しくすること | 広範囲かつ比較的近い距離 | 弱い |
サーキュレーターの目的は「空気を循環させること」
サーキュレーターの使用目的は、空気を循環させることです。送風できる範囲は狭いものの、強い風をまっすぐ遠くまで送ることができます。
扇風機の目的は「涼しくすること」
扇風機の本来の目的は、室内を涼しくすることです。サーキュレーターと比較すると風が弱く、送風できる距離は短いですが、ファンが大きいため広範囲に風を送ることができます。
関連記事:暑い部屋を涼しくする方法を徹底解説!エアコンなしでも快適に過ごす秘訣とは?
サーキュレーターと扇風機の電気代、どっちが高い?
サーキュレーターと扇風機の使用目的をお伝えしましたが、電気代についてはどちらが高いのでしょうか。計算方法を含め、具体的な金額の目安を紹介します。
関連記事:【最新】扇風機の電気代は安い?エアコンとの比較や節約術を解説!
電気代の計算方法とは?
電化製品の電気代は、以下の2つの方法で計算できます。
・電気代(円)= 消費電力(kW)× 電気代の単価(円/kWh)× 時間(h)
・電気代(円)= 消費電力量(kWh) × 電気代の単価(円/kWh)
消費電力は製品カタログなどで確認できますが、ワット(W)表示の場合がほとんどです。その場合は1,000で割ってキロワット(kW)に換算しましょう。
電気代の単価について、本記事では税込31円/kWhを使用します(※2024年9月時点で公益社団法人 全国家庭電気製品 公正取引協議会が定めた目安単価)。
関連記事:電気代の計算方法は?内訳や電気料金を安くする方法をわかりやすく解説!
関連記事:【2025年最新】電気代が高いのはなぜ?電気料金の平均額と値上げする理由、安くする方法を解説
サーキュレーターと扇風機の電気代を徹底比較!
続いて、サーキュレーターと扇風機の電気代を見ていきましょう。今回はそれぞれ3つずつ、特徴が異なる製品ごとの電気代を紹介します。
| 種類 | 1日あたりの電気代 | 1ヶ月あたりの電気代 | 1年間あたりの電気代 | |
| サーキュレーター | ACモーター(8畳用) | 5.0円 | 150.0円 | 1,800.0円 |
| DCモーター(20畳用) | 5.7円 | 171.0円 | 2,052.0円 | |
| DCモーター(30畳用) | 8.7円 | 261.0円 | 3,132.0円 | |
| 扇風機 | 3Dサーキュレーター (3枚羽根・10畳用) |
3.7円 | 111.0円 | 1,332.0円 |
| リビングファン (7枚羽根・10畳用) |
5.0円 | 150.0円 | 1,800.0円 | |
| リビングファン (5枚羽根・10畳用) |
10.9円 | 327.0円 | 3,924.0円 |
(出典:PCF-SDS15T-EC、PCF-SDC18T|アイリスオーヤマ株式会社、PJ-R3DS、PJ-R3AS、PJ-R2DS|シャープ株式会社)
1日あたりの電気代は、サーキュレーターが5〜8.7円で、扇風機が3.7〜10.9円です。扇風機の方が電気代の幅が広いものの、平均はどちらも約7円と大きな違いはありません。
1年間あたりの電気代でみても、サーキュレーターが1,800〜3,132円で扇風機が1,332〜3,924円となっており、上限も下限もわずか数百円差です。ここからもわかるように、サーキュレーターと扇風機の電気代はほぼ同じといえます。
さらに、サーキュレーターでいえばDCモーター、扇風機でいえば7枚羽根のように、機能が充実してる製品ほど消費電力が増え、電気代が高くなることもわかりました。
関連記事:【2025年】電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、家庭でできる節約術を解説!
関連記事:【2025年】電気代の補助金制度とは?補助内容をわかりやすく解説!
エアコンの電気代はサーキュレーター併用で安くできる
サーキュレーターは風を送るのが目的と説明しましたが、エアコンと併用することで電気代を安くすることもできます。
これはサーキュレーターの風が空気を効率よく循環させるため、エアコンの温度設定を控えめにしても快適な状態が維持できるからです。
「エアコンの電気代が高いので困っている」という方は、サーキュレーターと併用することも検討するといいでしょう。
関連記事:暖房の設定温度は何度が理想?電気代を節約しつつ快適に過ごすコツとは?
関連記事:エアコンの電気代はいくら?1時間ごとの計算方法や節約術をわかりやすく解説!つけっぱなしの方が安い?
サーキュレーターと扇風機はどちらがおすすめ?
サーキュレーターと扇風機の電気代について解説してきましたが、果たしておすすめはどちらなのでしょうか。
結論からいえば、「シーンによって使い分ける」のがベストです。ここでは、それぞれに適した使い方を紹介します。
①エアコンを効率よく使いたいなら「サーキュレーター」
前述したように、エアコンを効率よく使うにはサーキュレーターとの併用がおすすめです。
エアコンの風には冷たいと下、暖かいと上にたまる性質があります。その影響により、冷房や暖房を使うと特定の場所しか冷えない、暖まらないなどの「温度ムラ」が生じやすいです。
サーキュレーターがあればこの温度ムラが解消されるため、エアコンの余計な稼働を減らすことができます。
②あまりエアコンを使わないなら「扇風機」
あまりエアコンを使わない場合は、扇風機を活用しましょう。広範囲に風を送れるため、涼むことが目的のシーンで重宝します。また扇風機は風の強さが控えめという点で、冷え性や乾燥肌の方にもおすすめです。
どうしてもサーキュレーターを扇風機として利用したい、という場合はサーキュレーター・扇風機一体型の機種を使うといいでしょう。省スペースなうえ、本体価格も抑えられて一石二鳥です。
③洗濯物を室内干しするなら「サーキュレーター」
洗濯物を室内干しするシーンでは、サーキュレーターが活躍します。継続的に強い風を当てると衣類の水分が早く蒸発し、生乾き臭・雑菌の発生を防げるのです。梅雨時はもちろん、一人暮らしで防犯面が気になる場合もぜひご活用ください。
④寝るときに使うなら「扇風機」
寝るときに使う場合は扇風機がおすすめです。サーキュレーターよりも静音性に優れているうえ、やわらかい風が快眠をもたらしてくれます。
ただ、いくら風が弱めの扇風機でも、つけっぱなしで寝る際は健康への配慮が必要です。首振り機能やタイマー機能を使うなどして、長時間風に当たり続けないよう気をつけましょう。
おすすめシーン別にまとめると
前項まで紹介したサーキュレーターと扇風機、それぞれのおすすめシーンをふり返りましょう。
・エアコンを効率よく使いたい場合:サーキュレーター
・あまりエアコンを使わない場合:扇風機
・洗濯物を室内干しする場合:サーキュレーター
・寝るときに使う場合:扇風機
使い分けに悩んだときは、上記を参考にしてみてください。
サーキュレーターと扇風機の効果的な活用方法
サーキュレーターと扇風機のおすすめの使い方がわかったところで、今度はそれぞれの効果的な活用方法を6つ見ていきましょう。
①冷房と併用するならエアコンに背を向ける
冷房と併用する場合、サーキュレーターや扇風機はエアコンを背にした場所に置きましょう。なおかつエアコンの真下あたりで運転させれば、下方にたまりやすい冷たい空気を効率よく循環できます。
また、サーキュレーターや扇風機の風向きを「上向き」にするのもコツです。下から真上に向かう風が、冷気を部屋の隅々まで拡散します。
関連記事:扇風機とエアコンの電気代はどっちが安い?併用で効果的に節約する方法も解説!
関連記事:エアコンのドライ(除湿)とは?電気代や冷房との違い、節約方法をわかりやすく解説!
②暖房を使うなら部屋の隅に設置する
暖房を使う場合、サーキュレーターや扇風機は部屋の隅に設置しましょう。それによって、暖かい空気が部屋全体に効率よく行き渡ります。さらに、エアコンに対して対角線上に置くことで、暖房の効果がより高まります。
また、暖かい空気が天井周辺にたまりやすいことをふまえ、サーキュレーターと扇風機の風向きを「上向き」に調整するのもポイントです。
関連記事:エアコンの暖房の電気代は高い?節約方法もあわせて解説!
関連記事:【最新】電気代が安い暖房器具はこれ!コストを徹底比較、節約術も紹介!
③換気や乾燥したいなら窓の外に向ける
換気や乾燥が目的の場合、サーキュレーターや扇風機は窓の外に向けて設置しましょう。こうすることで、部屋にこもった空気を効率よく外に逃せます。
もし部屋に窓がなければ、ドアを全開にしたうえでドアの外に向け、サーキュレーターを設置しましょう。それにより、部屋にこもった空気を排出しながら室外の空気を取り込むことが可能です。
④ロフトに冷気を送るなら2台使用もアリ
サーキュレーターや扇風機でロフトに冷気を送る場合は、2台使用がおすすめです。
1台は、ロフトに置くためのものです。風向きが「天井向き」になるよう設置し、ロフト・天井それぞれの周りにたまった熱気を逃しましょう。
もう1台は1階に設置します。エアコンを背にロフト方向へ空気を循環させれば、1階にたまった冷気を効率よく分散することが可能です。
⑤外の気温によって置き方を変える
サーキュレーターや扇風機を単独で使う場合、外の気温に応じて置き方を変える必要があります。
室内より外が暑いときは窓付近に置き、外向きに風を送りましょう。これによって屋外の熱気が入るのを防ぐことができ、涼しい状態を保つことができます。
室内が外より暑いときは、窓を開けてその近くにサーキュレーター、扇風機を置きましょう。風が室内方向に流れるようにすることで、屋外の冷たい空気を効率よく取り込めます。
⑥エアコンを使わないなら氷を前に置く
エアコンを使いたくない場合、サーキュレーターや扇風機の前に氷を置く方法も効果的です。氷は溶けて蒸発する際、気化熱で周りの熱を奪う性質があります。そうして冷えた空気が室内に循環すれば、部屋全体が涼しく感じられるでしょう。
氷は洗面器、バケツなどにそのまま入れてもいいですが、水を入れたペットボトルを凍らせて使う方法もあります。
関連記事:カーボンニュートラルとは?意味や背景、実現に向けた世界の取り組みをわかりやすく解説
サーキュレーターを購入する場合のポイント
サーキュレーターを購入する場合、事前に押さえておきたいポイントは次の5つです。
①対応畳数は適切か
まずは、対応畳数が適切かどうか確認しましょう。サーキュレーターは機種ごとに出力や羽のサイズが違い、それによってカバーできる畳数が変わります。一般的に対応畳数が大きいものほど、風量が強くなるとされています。
空気循環のしやすさは環境に左右されるため、実際の間取りよりやや大きめの対応畳数を選んでおくと安心です。必要以上に大きいと風が強すぎるため、ワンサイズほど上のものを選ぶのがおすすめです。
②満足できる風力か
サーキュレーターの風力が満足できるかどうかも、購入前にチェックしましょう。風力を知るには、前項の対応畳数ほか、何m先まで送風できるかを示す「到達距離」も目安となります。
部屋の大きさに対して風力が小さい機種を選んでしまうと、室内の空気循環が非効率になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
③静音性が期待できるか
続いて確認したいのが、静音性に期待できるかどうかです。
サーキュレーターは風力が強い分、扇風機と比べて動作音が大きい傾向があります。寝室や書斎などの静かな部屋で使う場合は、静音性に優れたモデルを選ぶのがおすすめです。
④求めている機能があるか
求めている機能があるかも、サーキュレーターの購入時に重視したいポイントです。代表的な機能には、「首振り機能」と「タイマー機能」の2つがあります。
首振り機能においては、どれだけ角度を調節できるかも大切です。上下左右に首振りできるタイプを選べば、空気循環の効率性が大幅にアップすることもあります。
⑤お手入れできるか
購入後、自分でお手入れできるかどうかも必ず確認しましょう。サーキュレーターは、羽根周辺にホコリがたまりやすいアイテムです。定期的な掃除を前提とする場合、お手入れのしやすさは使い勝手を大きく左右します。
おすすめなのは、カバーを外せるタイプです。先にカバーを取り外すことで掃除を効率よく進められるほか、怪我の予防にもつながります。
サーキュレーターを購入する場合のポイントをまとめると
ここまで解説してきた、サーキュレーター購入時のポイントは次の5つです。
・対応畳数は、実際の間取りよりワンサイズ上にする
・到達距離などを参考に、部屋の大きさに合った風力か確認する
・なるべく静音性に優れたモデルを選ぶ
・求める機能があるかどうかチェックする
・お手入れしやすいよう、カバーが外せるタイプを選ぶ
今後サーキュレーターを購入する際は、上記を意識して選ぶことをおすすめします。
扇風機を購入する場合のポイント
扇風機を購入する際は、次の6つのポイントを意識しましょう。
①ニーズに合った形かどうか
扇風機は使うシーンを想定したうえで、ニーズに合った形を選ぶことが大切です。具体的な種類には、次の4つがあります。
リビング扇(リビングファン)
リビング扇(リビングファン)は、現在最もスタンダードな扇風機です。モーターで羽根を回して風を起こす仕組みを採用しており、国内では古くから愛用されています。風量の切り替えや風向きの調整ができるほか、先述した首振り機能やタイマー機能を搭載するモデルが多いのも特徴です。
タワー扇(タワーファン)
タワー扇(タワーファン)は、名前の通りタワー型の扇風機です。スリムな形状で設置スペースをとらず、デザイン性の高い機種として注目されています。最大の特徴は、「羽根がないこと」です。従来のリビング扇と違い、小さな子供やペットがいる場合も安心して使えます。
エアマルチプライアー(羽根なし扇風機)
エアマルチプライアー(羽根なし扇風機)は、2009年にダイソンが生み出した扇風機です。タワー扇の一つで羽根がないため、子育て世帯でも導入しやすいでしょう。最近は空気清浄機能や温冷機能などを搭載し、年間通して活躍する機種も増えています。
卓上扇(卓上扇風機)
卓上扇(卓上扇風機)は、デスク上などで使われる小型の扇風機です。クリップで固定できるタイプもあり、用途に応じて使い分けすることができます。
あらかじめ充電してから使う「充電式」やUSBケーブルで充電する「USB式」など、給電方法が豊富なのも特長です。持ち運び用の扇風機を探している場合は、この卓上扇が最適といえるでしょう。
②満足できる風量かどうか
満足できる風量かどうかも、扇風機を選ぶ際のポイントです。扇風機の風量は、一般的に羽根の枚数が少ないものほど、大きくなる傾向があります。
パワフルな風を求める場合は、羽根の枚数が3〜5枚ほどの機種がおすすめです。逆にやさしい風を求める場合は、少なくとも7枚ほど羽根がついたものを選ぶようにしましょう。
③静音性が期待できるか
次に確認したいのが、静音性に期待できるかどうかです。静音性の高さを確かめるには羽根の枚数が目安となります。基本的に枚数が少ないものほど、静かでなめらかな風を生み出すことが可能です。
突然運転音が気になり出した場合は、内部を丁寧に掃除してみましょう。風を切る羽根周辺にホコリがたまり、余計な動作音が生じているかもしれません。
④DCモーターかACモーターか
DCモーターとACモーター、どちらを搭載しているかも確認したいポイントです。
性能を重視したい方には、DCモーター搭載の扇風機をおすすめします。静音性に優れているほか、細かい風量調節により消費電力を抑えられ、電気代も節約できます。
一方のACモーターは、本体価格の安さが強みです。あまり扇風機を使わない家庭や、購入費用を抑えたい方は、こちらを選んでもいいでしょう。
⑤扇風機に求めている機能があるか
扇風機に求める機能があるかどうかも、事前にチェックしておきましょう。実際に使うシーンを想定し、必要な機能がそろったモデルを選ぶことが大切です。
中でもニーズの高い機能には、次のようなものがあります。
・タイマー機能(オン/オフ共に搭載)
・首振り機能(上下左右対応)
・リモコン操作(遠隔操作が可能)
・ヒーター機能や冷風機能(年間を通して利用できる)
・センサー機能(周囲に人がいない場合、自動でオフになる)
・脱臭/空気清浄機能(風を送るだけでなく、付加機能も備わっている)
⑥価格が高すぎないか
これは意外かもしれませんが、扇風機の本体価格は高すぎない方がいいです。扇風機は高いものほど多機能になることが多いですが、高すぎても単に余計な機能が増える恐れがあります。
価格を決める主な要素は、モーターの種類です。安価なACモーターは3,000円〜1万円程度、比較的高額なDCモーターは数万円〜5万円程度が相場となります。機能性を重視してDCモーターを選ぶにしろ、5万円もするようなモデルは避けるようにしましょう。
関連記事:【2025年】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!
関連記事:【2025年】二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!
関連記事:【2025年】4人家族の電気代平均はいくら?季節別や地域別の平均、料金が高い原因や節約方法をご紹介
サーキュレーターと扇風機の電気代を節約する方法とは
最後に、サーキュレーターと扇風機の電気代を節約する方法を6つ紹介します。
関連記事:【必見】エアコンの電気代の節約術を徹底解説!手軽に効率よく節電するコツとは?
関連記事:【2025年最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
関連記事:無料で電気代を安くする方法とは?電気料金の節約・削減方法をわかりやすく解説!
①エアコンと併用する
先述の通り、サーキュレーターと扇風機はエアコンとの併用で電気代を節約できます。両者の風で空気循環をよくすることで、室内の温度ムラを防いでエアコンの温度設定も控えめにできるためです。
エアコンは温度設定を多少変えるだけで、年間の電気代を確実に削減することが可能です。冷房でいえば、1℃上げた場合に約10%の節電効果があるとされています。
関連記事:【徹底解説】エアコンのつけっぱなしは節電にならない?電気代の節約方法も紹介!
関連記事:エアコンの電気代と節約術をわかりやすく解説!つけっぱなしはやめた方がいい?
②熱気を追い出すために使う
事前にサーキュレーターと扇風機を使い、室内の熱気を追い出すことも電気代の削減につながります。エアコンの冷気がスムーズに拡散され、従来より少ない電力でも部屋を快適にできるためです。
天井付近にたまった熱気は、窓を開けてもなかなか外に出ていきません。特に夏場は、サーキュレーターと扇風機による強制的な換気を惜しまないようにしましょう。
③タイマー機能をうまく活用する
タイマー機能をうまく活用する、という方法でも電気代を節約することが可能です。設定した時間になれば、自動でサーキュレーターと扇風機の運転がストップします。これにより消し忘れを防ぐことができ、余計な消費電力を発生させずに済みます。
部屋干しが多い場合には、長時間のタイマー機能がついた製品が適しています。洗濯物の生乾き臭を防ぐには5時間以内に乾燥するのが理想なので、余裕をもって約5時間のタイマー機能付きのサーキュレーター、扇風機を選ぶと安心です。
④DCモーターのあるものを購入する
DCモーター搭載のサーキュレーター、扇風機を購入することで、電気代が安くなるケースもあります。
ACモーター搭載の扇風機の電気代は、1時間あたり0.5〜1円程度です。一方のDCモーターは0.1〜0.6円程度で、1日あたり8時間の使用を想定すると約3.2円の金額差が生じます。
よってDCモーターは製品自体の価格が高めではあるものの、長い目でみればコストパフォーマンスに優れているといえるでしょう。
⑤新しいものに買い換える
新しいものへの買い換えにより、電気代を抑えられることもあります。サーキュレーターや扇風機のような電化製品は、新しいものほど省エネに特化している傾向があるためです。
現在ACモーター搭載の機種を使っているのであれば、電気代が安いDCモーター採用のものに買い換えることで、大幅な節約効果にも期待できます。
関連記事:【図解】JEPXとは?取引の仕組みや市場価格の決まり方をわかりやすく解説!
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
⑥電力会社を切り替える
ここまで紹介した5つの方法を試せば、サーキュレーターと扇風機の電気代は十分抑えられます。ただ、最も効果的な節約方法としておすすめなのは、「電力会社の切り替え」です。
先述した通り、サーキュレーターと扇風機の電気代は以下で求められます。
・電気代(円)= 消費電力(kW)× 電気代単価(円/kWh)× 時間(h)
・電気代(円)= 消費電力量(kWh) × 電気代単価(円/kWh)
前項まで解説してきたのは、ほとんどが上記のうち「消費電力(消費電力量)」を抑える方法です。 ただ、いくら節電しても、大きく消費電力を下げることはできないため、電気代の大幅なコストカットは難しいです。 効率よく電気代を安くするには「電気代の単価を下げる」ことが大切になります。
そして電気代の単価を下げる方法が「電力会社の切り替え」です。今よりも電気代の単価が安い電力会社にすることで、サーキュレーターと扇風機含む電化製品すべてにかかる電気代を下げることができます。
「手っ取り早く電気代を安くしたい・・・」という方は、ぜひ電力会社の切り替えを検討してみてください。
関連記事:【2025年】電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説!
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしませんか?
しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供しています。
このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。
 ※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、
※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、
しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。
また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。
環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みください。申込ページでは、プランの詳細についてわかりやすく説明しています。
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説
<その他オススメの関連記事>
冷蔵庫の電気代はいくらくらい?9つの節約方法もあわせて解説!
テレビは電気代が高い?種類ごとの電気代や節約方法をわかりやすく解説!
洗濯機の電気代と水道代は1回いくら?6つの節約術も徹底解説!
電子レンジの電気代はいくら?計算方法や6つの節約術をわかりやすく解説!他の電化製品とも徹底比較
パソコンの電気代はいくら?デスクトップやノート、ゲーミングPCの消費電力と節約方法をご紹介
オール電化の電気代は高い?高い原因や平均額、節約術をわかりやすく解説
ホットカーペットの電気代は高い?エアコンなどの暖房器具と比較して解説
電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説
【2025年最新】再エネ賦課金とは?仕組みや役割をわかりやすく解説!
再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!
電気代の燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説