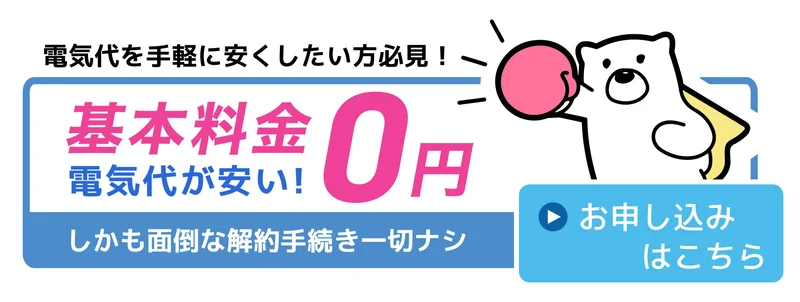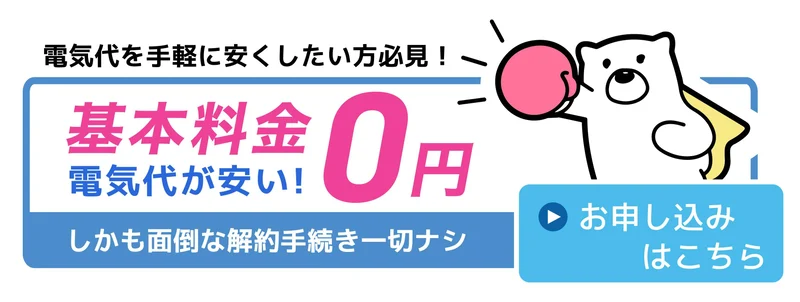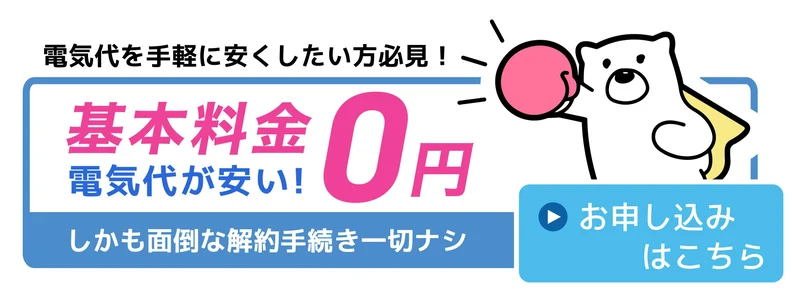kVA(キロボルトアンペア)は、電力を表す単位のひとつですが、初めて見聞きする方もいるでしょう。
本記事では、kVA(キロボルトアンペア)とはどういった意味を持つのか詳しく解説します。kW(キロワット)との違いや計算式、電気代の節約方法などにも触れているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:kWh(キロワットアワー)とは?kWとの違いや電気代の仕組み、節約術をわかりやすく解説!
関連記事:【最新】消費電力の計算方法をわかりやすく解説!電気代の求め方や節約方法も紹介
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
|
この記事を読んでわかること
・kVAとは何を意味するのか
・kVAとkWの違い
・kVAの計算式
・kVAを理解し電気代を節約する方法
|
kVAとは?

|
結論をまとめると!
・kVAとは電力の大きさを表す単位のひとつ
・kVAは、有効電力と無効電力の両方を含んだ総電力量を表している
|
kVA(キロボルトアンペア)とは、電力の大きさ(容量)を表す単位のひとつです。おもに電力の供給量や機器の性能を示すときに使われ、発電機や変圧器など、電力を供給する機器がどの程度の能力を持っているかを表す指標として用いられます。
kVAは、供給される「電力の総量」を示しています。電化製品を動かすためには電力会社から電気が送られますが、このとき供給される電力全体の大きさがkVAで表されるのです。
ただし、供給された電力のすべてを有効に利用できるわけではありません。多くは「有効電力」と呼ばれ、実際に電化製品を動かすために使われますが、一部の電力は「無効電力」と呼ばれ、熱などに変換されるためムダになるのです。
この「有効電力」と「無効電力」の総量を示す単位が「kVA」です。
関連記事:【図解】電力自由化とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
関連記事:電源調達調整費とは?独自燃調の仕組みと特徴をわかりやすく解説
関連記事:「市場価格調整単価」とは?電気代がまた上がる?仕組みと対策をわかりやすく解説
kVAとKWの違いとは?

|
結論をまとめると!
・kVAとkWの違いは「無効電力」を含むかどうか
|
ここまで、kVAとはどのような意味を持つのか解説しました。ここからは、kVAとkWの違いについて確認してみましょう。
kVAとkWの大きな違いは、「無効電力」を含むかどうかです。kVAは「無効電力」を含む総電力量を表し、kWは実際に家電製品を動かす際に消費する「有効電力のみ」を指します。
たとえば、エアコンなどの電化製品を動かす場合、実際に有効に使われる電力は供給された電力の約95%とされています。つまり、この95%分の電力がkWで表され、ムダを含む100%分の電力がkVAで表されるということです。
家庭では、とくにエアコンや冷蔵庫など、モーターを回転させる家電で無効電力が発生します。一方で、電球や電熱ヒーターのように、ほとんど有効電力だけで動作する機器では、電力のロスはほとんどありません。
そのため、一般的にはkVAの値がkWより大きくなることが多いですが、機器によっては両者の差が小さい場合もあります。
関連記事:非化石証書とは?仕組みや購入方法、企業が導入するメリットをわかりやすく解説
関連記事:託送料金とは?仕組みとレベニューキャップ制度をわかりやすく解説!
関連記事:【図解】市場連動型プランとは?電気料金の仕組みやメリットとデメリットをわかりやすく解説
家庭での消費電力はkWを参考にしよう!
ここまでの内容をまとめると、kVAは「無効電力」を含む総電力量を表し、kWは実際に消費される「有効電力」のみを指すことがわかりました。
つまり、家庭や職場で電力の総供給量を知りたい場合はkVAを、実際にどれだけ電気を使っているかを知りたい場合はkWを参考にするとよいでしょう。
関連記事:【最新】4人家族の電気代平均はいくら?季節別や地域別の平均、料金が高い原因や節約方法をご紹介
関連記事:【最新】二人暮らしの電気代の平均はいくら?節約術や2人の光熱費の平均もわかりやすく解説!
関連記事:【最新】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!
kVAはどのようなシーンで活用するのか?

|
結論をまとめると!
・kVAは、電力を供給する機器や大量の電力を使う場所で活用される
・電気の使用量が多い一般家庭では契約の際にkVAが使われる
|
ここまで、kVAとkWの違いについて解説しました。ここからは、kVAはどのようなシーンで活用するのかを解説します。
kVAはおもに、発電機や変圧器など電力を供給する機器や、工場・商業ビルといった大量の電力を使う場所で活用されます。
kVAは、ムダになる電力(無効電力)も含めた、電力の合計を表しています。そのため、機械を動かすためにどれくらいの電気が必要なのかを予測することが可能です。
たとえば、新しくオフィスビルを建てる場合、そのビル全体で必要な電力量をkVAで計算します。また、停電に備えて発電機を設置するときも、使用する機械すべてを動かせるように、必要なkVAの容量をもとに選ぶのです。
さらに、データセンターのようにコンピューターを24時間稼働させる施設でも、安定した電力を保つためにkVAが活用されています。kVAは、電気を安全かつ安定して使うために、発電設備の設計や契約、運用計画を立てる際の大切な指標となっています。
家庭ではあまりなじみのない単位ですが、オール電化住宅や電気自動車を使用している家庭など、電気の使用量が多い場合は契約のときにkVAが使われることも多いです。
関連記事:全館空調の電気代は高すぎる?エアコンと比較すると?節約方法もわかりやすく解説!
関連記事:空気清浄機の電気代は高い?24時間つけっぱなしでも大丈夫?節約方法も解説
関連記事:従量電灯とは?プランごとの電気料金の仕組みや計算方法、節約術をわかりやすく解説
kVAの計算方法を解説!

|
結論をまとめると!
・kVA(キロボルトアンペア)= V(ボルト)× A(アンペア)÷ 1,000
・kW(キロワット) = kVA(キロボルトアンペア) × 力率
・力率 = kW(キロワット)÷ kVA(キロボルトアンペア)
|
ここまで、kVAのおもな活用シーンについて解説しました。ここからは、kVAの計算方法をご紹介します。
関連記事:【最新】世帯別・季節別・地域別の電気代平均は?電気料金の下げ方・節電方法もわかりやすく解説
関連記事:電気代の基本料金とは?仕組みと種類、電気料金を安くする方法をわかりやすく解説
関連記事:契約アンペアは変更すべき?変更方法やメリットをわかりやすく解説!
kVAを求める計算式
まず押さえておきたいのが、kVAを求める基本的な計算式です。kVAはV(ボルト)と(アンペア)の掛け合わせなので、そのまま言葉の通りに計算すると求められます。
また、k(キロ)= 1,000を意味するため、VAをkVAに変換するために1,000で割るとよいでしょう。
以上のことから、kVAの計算式は、次のようになります。
|
kVA(キロボルトアンペア)= V(ボルト)× A(アンペア)÷ 1,000
|
たとえば、電圧が200Vで電流が15Aの家電の場合、kVAの計算式は次のようになります。
|
kVA(キロボルトアンペア)= 200V(ボルト) ×15A(アンペア)÷ 1,000 = 3kVA
|
以上のように、機器の電圧と電流が分かっていれば、発電機などで必要とされる電源容量の目安であるkVAを算出することが可能です。
関連記事:【最新】わが家の電気代は高い?家庭の平均額や高くなる原因、節約術を解説!
関連記事:電気代の内訳の見方と計算方法とは?電気代を安くする方法もわかりやすく解説!
関連記事:【すぐ解決】ブレーカーが落ちる原因と復旧方法はコレ!予防策も紹介します
kVAをkWに変換する方法
次に、kVAをkWに変換する方法をご紹介します。kVAからkWへの変換には、力率という数値を使います。力率とは、供給された電力のうち、実際に使われた電力の割合(効率)を表す数値です。
kVAをkWに変換する計算式は以下のようになります。
|
kW(キロワット) = kVA(キロボルトアンペア) × 力率
|
たとえば、力率が0.9で無効電力が3kVAの家電の場合、kVAをkWに変換する計算式は次のようになります。
|
kW = 3kVA × 0.9(力率)= 2.7kW
|
以上のことから、この家電で実際に使用される消費電力は2.7kWで、無効電力は0.3kWであることがわかります。
関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!
関連記事:【図解】電気代を左右する燃料費調整額とは?仕組みや今後の見通し、安くする方法をわかりやすく解説
関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説!
kVAの理解に欠かせない「力率」について
力率とは、総電力量であるkVAのうち、実際に有効に利用できる割合を示す数値です。たとえば、エアコンなどの電化製品が総電力量の95%を有効に消費している場合、力率はこの95%を指します。
力率の計算式は、次のとおりです。
|
力率 = kW(キロワット)÷ kVA(キロボルトアンペア)
|
たとえば、700Wの電化製品に対して総電力が760VAである場合の力率は次のように計算します。
この場合、力率は0.921であり、パーセントで表すと92.1%になります。
力率は0から1の値で表され、一般的な家電製品では0.8~1.0の範囲に収まることが多いです。力率の最大値は1(100%)で、この値が高いほど電力を効率よく使えていることを意味します。
力率が1であれば無駄がなく「kVA = kW」となりますが、モーターを使用する機器などでは、力率が0.8(80%)程度に低下することもあります。
関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
関連記事:【最新】電気代の再エネ賦課金とは?単価の推移、値上げの理由と今後の予想をわかりやすく解説!
関連記事:電力需給のひっ迫はなぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げリスクも!概要と法人がすべき対策を解説
kVAを理解すると電気代の節約にも役立つ!

|
結論をまとめると!
・力率の高い家電製品の使用は、電気代の基本料金を抑えられる可能性がある
・力率の高い家電製品は、電気設備の故障リスクを減らしたり機器の寿命を延ばしたりするメリットがある
|
kVAの知識は、実は電気代の節約にもつながります。
kVAとkWの関係を理解すれば、電気設備がどれだけ効率的に電力を使用しているかが分かるようになります。力率の低い家電製品を使用していると、必要以上に大きな電力を消費してしまい、その結果、基本料金が高くなることがあるのです。
たとえば、企業や工場では契約電力がkVAやkWで決められており、力率を改善することで基本料金を下げられます。一般家庭でも、オール電化住宅などkVAで契約容量が決まる場合、力率の高い省エネ家電を選ぶことで基本料金を節約できる可能性があるのです。
また、力率が高い電化製品は、家庭内の配線への負担が少ないため、設備の故障リスクを減らしたり機器の寿命を延ばしたりするメリットもあります。
関連記事:オール電化の電気代は高い?高い原因や平均額、節約術をわかりやすく解説
関連記事:電気代が高い家電ランキング10選|年間の電気代や節約方法も解説!
関連記事:使ってないのに電気代が高い原因とは?調べ方や対処法を解説!
kVAへの理解を活かして電気代を賢く節約する方法!

|
結論をまとめると!
①電化製品を買い替える
②電気契約を見直す
③電気代の安い電力会社に乗り換える
|
ここまで、kVAを理解すると電気代の削減につながることを解説しました。ここからは、kVAへの理解を活かして電気代を賢く節約する方法を3つご紹介します。
関連記事:【必見】絶対すべき節約術を紹介!やってはいけない節約方法も解説します
関連記事:【必見】一番節約できるものはどれ?すぐできるものとNGな節約方法もわかりやすく解説!
関連記事:1,000Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?おもな家電の電気代や節約術も解説!
①電化製品を買い替える
電気代を節約する1つ目の方法は、力率の高い省エネ家電への買い替えです。
古い電化製品は力率が低く、電気を効率的に使えていない場合があります。最新の省エネ家電は力率が改善されており、同じ仕事をするのに必要な電力量が少なくて済むのです。
たとえば、最新のエアコンや冷蔵庫は、10年前と比べて消費電力が大幅に改善されています。

引用元:一般社団法人 家電製品協会「2025年版スマートライフおすすめBOOK」
上図は、10年前のエアコンと最新の省エネタイプの消費電力を比較したものです。最新の省エネタイプは、10年前のエアコンに比べて年間約3,810円の電気代を節約できることがわかります。
電化製品の買い替えは初期費用はかかりますが、長期的に見れば電気代の削減につながる場合が多いです。とくにモーターを使うエアコンや冷蔵庫、洗濯機などは、買い替えによる節電効果が大きいといえます。
環境省が提供する「しんきゅうさん」などの情報サイトでは、電化製品の型番から消費電力を比較することも可能です。気になる方は、ぜひ一度利用してみてください。
関連記事:【最新】電気代が安い暖房器具はこれ!コストを徹底比較、節約術も紹介!
関連記事:【最新】電気代・ガス代の補助金制度をわかりやすく解説!政府の補助金額や期間、電気料金を安くする方法とは?
関連記事:1,200Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?家電別の電気代や節約術も解説!
②電気契約を見直す
電気代を節約する2つ目の方法は、現在契約している電力プランを見直すことです。力率の高い電化製品を使用している場合、契約アンペアを少なくすることで基本料金を下げられる可能性があります。
また、改めて現在のライフスタイルでの電化製品の使い方を見直してみると、より適切なプランが見つかり電気代を安くできるかもしれません。たとえば、日中は外出していることの多い家庭では、夜間の電気代が安くなるプランに変更すると、月々の電気料金を安くできます。
電気料金プランは電力会社により異なるため、気になる方はぜひ調べてみてください。
関連記事:【2025年最新】電気代の見直しで安くするためのポイントとは?具体的な方法や注意点も解説!
関連記事:電気の契約はどう進める?引越し・現住所それぞれの進め方や即日開通についても解説!
関連記事:【最新】無料で電気代を安くする方法を徹底解説!電気料金を安くしたい方必見!
③電気代の安い電力会社に乗り換える
電気代を節約するためのもっとも手軽な方法が「電気代の安い電力会社への乗り換え」です。
2016年の電力自由化により、私たちは自由に電力会社を選べるようになりました。会社により料金プランや電気料金単価が異なるため、乗り換えるだけで電気代を削減できる可能性があります。
たとえば、公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電気代の単価の相場は31円/kWhですが、25円/kWhなどもっと安い電力会社はたくさんあるのです。電気代単価の安い電力会社に変えると、同じ電気の使用量でも毎月の電気代を手間なく削減できます。
また、なかには電気代の単価が安いだけでなく、基本料金が無料で月々の電気代を無理なく抑えられるところもあります。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
関連記事:電力会社・電気料金プランの選び方とは?注意点と電気代を安くする方法を解説
関連記事:【最新】電気代を値上げする電力会社一覧!電気料金はどれくらい高くなる?
基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしませんか?
しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供しています。
このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。
また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。
環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みください。申込ページでは、プランの詳細についてわかりやすく説明しています。