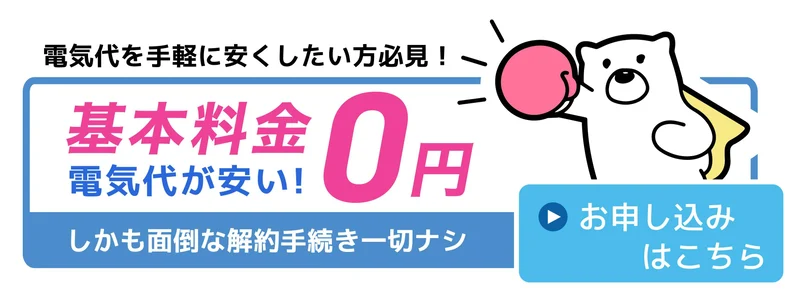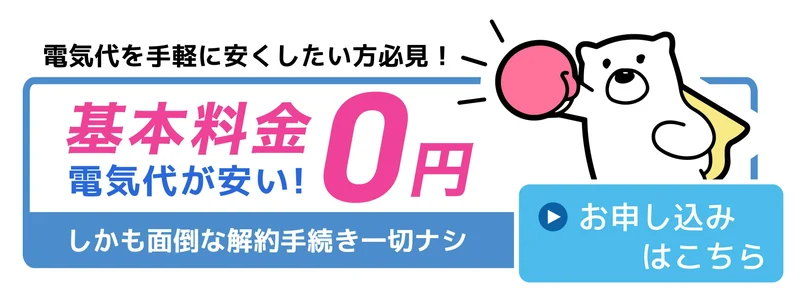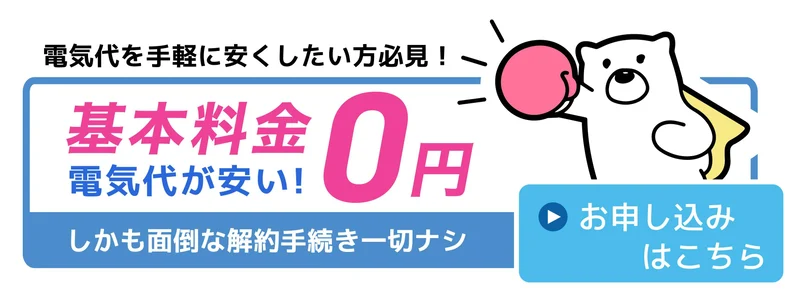一人暮らしの初期費用が高い!コストを抑えるコツ10選を解説

|
結論をまとめると!
・一人暮らしの初期費用は工夫をすることで確実に安くなる
|
ここまで、一人暮らしの初期費用が実際にいくら必要なのかを解説しました。ここからは、一人暮らしの初期費用が高くてコストを抑えたい場合の節約のコツを10選ご紹介します。
関連記事:夜にエアコンをつけっぱなしにした場合の電気代は安い?節約方法も解説!
関連記事:エアコンの消費電力はどれくらい?電気代の計算方法や節約術についても解説!
関連記事:エアコン掃除は自分でできるのか?掃除の手順や注意点も解説!
①家賃の安い物件を探す
一人暮らしの初期費用をおさえるために一番効果的なのは、家賃の安い物件を選ぶことです。
賃貸契約にかかる費用は初期費用のなかでももっとも高いため、可能な範囲で家賃を抑えることができれば全体の金額も下がります。また、家賃は毎月支払う固定費でもあるため、最初に安い物件を見つけられると長期的な節約にもつながります。
家賃を抑えるためには、駅から少し離れたり、築年数が古い物件を探したりするとよいでしょう。ただし、駅からあまりに離れると、バス代や駐輪所をはじめとした交通費が余計にかかる可能性もあるため注意が必要です。
無理なく生活できる範囲で、少しでも安い家賃の物件を選びましょう。
関連記事:電気がつかない原因とは?適切な対処法や注意点についても解説!
関連記事:使ってないのに電気代が高い原因とは?調べ方や対処法を解説!
②敷金・礼金ゼロ(ゼロゼロ物件)の物件を選ぶ
敷金・礼金がゼロの物件を選ぶのも、一人暮らしの初期費用を抑えるのに効果的です。
最近では、敷金・礼金が必要ない「ゼロゼロ物件」といったものが増えています。通常、敷金や礼金は家賃1~2か月分がかかるため、ゼロにできると初期費用を数万円から十数万円抑えられます。
ただし注意したいのが、敷金・礼金ゼロの物件は、家賃が高かったり退去時に清掃費が必要だったりする場合があることです。そのため、契約時にはしっかりと内容を確認し、住む期間も合わせて考慮しましょう。
関連記事:電気代はどれくらい値上げした?推移と今後の予測、法人・家庭でできる電気料金の高騰対策を解説!
関連記事:【最新】無料で電気代を安くする方法を徹底解説!電気料金を安くしたい方必見!
③フリーレント付き物件を選ぶ(一定期間家賃無料)
フリーレント付き物件を選ぶことも、初期費用を大幅に抑える有効な手段です。
フリーレントとは、入居後の一定期間(1〜2ヶ月間程度)の家賃が無料になる契約形態を指します。初期費用には通常、入居月や翌月分の「前家賃」が含まれますが、フリーレントによってこの部分が免除されるため、初期費用の総額を大きく減らすことができます。
たとえば、家賃7万円の物件で1ヶ月のフリーレントが付いている場合、前家賃分の7万円が不要になります。
ただし、フリーレント付き物件は短期間での解約に違約金が設定されている場合もあるため、契約内容は必ず確認しましょう。
関連記事:【最新】電気代の値上げを徹底解説!電気料金が高騰する理由と対策とは?
関連記事:【最新】今後も電気代は値上げする?高い原因と予測、法人・家庭でできる電気代削減方法を徹底解説
④仲介手数料が安い物件を探す
仲介手数料が安い、あるいは無料の物件を選ぶことも、初期費用削減に直結します。
仲介手数料は、物件を紹介・契約してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律で「家賃1ヶ月分+消費税」が上限と定められていますが、物件によっては半額や無料に設定している場合があります。
大家さんが早く借り手を見つけたい物件や、不動産会社が自ら「貸主」となっている自社物件では、仲介手数料がかからないケースが多く見られます。「仲介手数料無料」や「仲介手数料半額」といった条件で物件を検索してみることも、賢い節約術のひとつです。
関連記事:【すぐ解決】ブレーカーが落ちる原因と復旧方法はコレ!予防策も紹介します
関連記事:【図解】エコキュートとは?仕組みやガス給湯器の違い、メリットをわかりやすく解説!
⑤家具家電付きの物件を探す
家具家電付きの物件を選ぶと、引越し時にかかる家具・家電の購入費用を節約できます。
一人暮らしを始める際は、家具や家電を一度に揃える必要があり、大きな出費となります。家具家電付き物件であれば、生活に必要な最低限のものが最初から備え付けられているため、個別に購入する費用と手間を削減できるのです。
ただし、家具・家電が備え付けになっている分、月々の家賃が相場より高めに設定されている可能性があります。 そのため、住む期間を考慮し、トータルでどちらがお得になるか判断することをおすすめします。
長く住む場合は、自身で家具を買い揃えた方が結果的に安い場合もあるでしょう。
関連記事:【必見】エアコンの電気代の節約術を徹底解説!手軽に効率よく節電するコツとは?
関連記事:ドラム式洗濯機の電気代はいくらぐらい?縦型洗濯機の電気代との比較や節約術も解説!
⑥日割り家賃がかからないようにする
入居日を調整し、日割り家賃の発生を最小限にすることも、初期費用を抑える工夫のひとつです。 月の途中で入居する場合は、その月の日割り家賃と翌月分の家賃(前家賃)をまとめて支払うのが一般的です。
たとえば、家賃6万円の物件に10月15日に入居すると、10月分の日割り家賃(約3万円)と11月分の前家賃(6万円)の合計約9万円が必要になります。もし入居日を11月1日にできれば、初期費用として支払う家賃は11月分の6万円のみで済みます。
不動産会社や大家さんと交渉し、可能であれば入居日を月初(1日)に設定できないか相談してみるとよいでしょう。
関連記事:オイルヒーターの電気代は高すぎる?他の暖房器具との比較や節約方法を解説!
関連記事:床暖房の電気代はいくら?エアコンより高い?節約方法もあわせて解説!
⑦引越し時期を閑散期にずらす
可能であれば、引越し時期を不動産業界の「閑散期」にずらすことで、初期費用を抑えられる可能性があります。
1~3月は、新入生や新社会人の引越しが集中する「繁忙期」です。この時期は需要が高いため、物件の家賃交渉が難しく、引越し業者の料金も高めに設定されています。
一方で、梅雨時の6~8月頃や11~12月頃は「閑散期」とされています。この時期は空室を避けたい大家さんが家賃や敷金・礼金の交渉に応じてくれやすかったり、引越し業者の割引が利用できたりするメリットがあります。
引越し時期を自身で決められる状況であれば、繁忙期を避けて物件探しを計画することをおすすめします。
関連記事:冷蔵庫の電気代はいくらくらい?9つの節約方法もあわせて解説!
関連記事:スマートメーターとは?従来のメーターとの違い、メリットや仕組みをわかりやすく解説
⑧家具家電を中古品やレンタルで揃える
家具や家電をすべて新品で購入せず、中古品やレンタルサービスを利用することで、初期費用を大幅に削減できます。
家具・家電は生活に必須なものですが、すべてを新品で揃える必要はありません。リサイクルショップやフリマアプリなどを活用すれば、中古品を安く入手できます。
また、最近では家具・家電のサブスクリプション(レンタル)サービスも増えており、月額料金で必要なものだけを借りることも可能です。こだわりたいもの以外は中古品やレンタルを賢く組み合わせることで、初期費用を大きく削減できる可能性があります。
関連記事:1,200Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?家電別の電気代や節約術も解説!
関連記事:1,000Wの電化製品の電気代はいくらぐらい?おもな家電の電気代や節約術も解説!
⑨引越し費用を抑える
賃貸物件の契約費用だけでなく、引越し業者に支払う「引越し費用」も、工夫次第で安く抑えることが可能です。
引越し費用は、荷物の量や移動距離、引越しの時期や時間帯によって大きく変動します。とくに繁忙期や土日祝日の午前中は料金が高くなる傾向にあります。
費用を抑えるためには、複数の引越し業者から見積もりを取る「相見積もり」が有効です。また、引越し日を平日の午後にしたり荷造りを自分でおこなうプランを選んだりといった方法もあります。
荷物が少ない場合は、宅配便や自力での運搬も検討し、状況に合ったもっとも安い方法を選びましょう。
関連記事:電力需給のひっ迫はなぜ起きる?いつまで続く?電気代値上げリスクも!概要と法人がすべき対策を解説
関連記事:再生可能エネルギーとは?メリット・デメリット、種類の一覧を簡単に解説!
⑩電気代が安い電力会社と契約する
電気代は厳密に言うと初期費用には含まれませんが、今後継続して払い続ける料金であるため、引越しを機に見直すのがおすすめです。
2016年の電力自由化以降、私たちは自由に電力会社を選べるようになりました。従来の大手電力会社よりも安価な料金プランを提供している新電力会社が多数存在しているのです。
とくに一人暮らしの場合、日中は学校や仕事で外出していることが多いため、夜間の電気代が安くなるプランや基本料金が0円のプランが適している場合があります。引越しの手続きと同時に、自身のライフスタイルに合った電力会社を比較検討してみましょう。
関連記事:【2025年最新】電気代の見直しで安くするためのポイントとは?具体的な方法や注意点も解説!
関連記事:【図解】新電力とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説!
関連記事:【最新】一人暮らしの電気代の平均はいくら?高い原因や節約方法を紹介!
住み始めてからの生活費を抑えるためには安い電力会社を選ぶのがおすすめ!

|
結論をまとめると!
・電気代を安くできると新生活の月々の支払いがラクになる
・電気代を抑えるためには安い電力会社を選ぶのがおすすめ |
一人暮らしは初期費用を支払えば終わりではなく、ここから新たな生活がスタートします。
2024年に実施された総務省統計局の家計調査結果によると、全国の一人暮らしの生活費の平均は169,547円でした。しかし、この調査の家賃の平均額は23,372円で計算されており、実際の都市部での月々の生活費はプラス5万円ほどかかると推測できます。
そうなると都市部での月々の一人暮らしの生活費は20万円を超えるため、高いと感じる方も多いのではないでしょうか。
月々の生活費を節約する方法はさまざまですが、電気代を安くできると継続的な支払いもラクになります。電気代は、「消費電力×電気代の単価」で決まるため、単価の安い電力会社を選ぶと無理なく月々の電気代を抑えられます。
電力会社のなかには月々の基本料金が0円のところもあり、無理なく節約することが可能です。安い電力会社を選ぶと、電気の使用量を減らすことなく月々の電気代を抑えられるため、一人暮らしの毎月の出費も抑えられるでしょう。
関連記事:電気の契約はどう進める?引越し・現住所それぞれの進め方や即日開通についても解説!
関連記事:電力会社を乗り換える方法とは?切り替え方法とメリット・デメリット、注意点を解説
関連記事:一人暮らしの生活費はいくらぐらい?内訳や年収別のシミュレーションも紹介!
基本料金0円!しろくまプランで電気代をもっと安くしませんか?
しろくま電力では、家庭・低圧法人を対象とした電力プラン「しろくまプラン」を提供しています。
このプランの特徴は「基本料金が0円」であること。それ以外の単価も、以下のように大手電力会社より安いケースがほとんどです。電力を切り替えるだけで、節電をしなくても電気代を安くできる可能性が非常に高いのです。

※ここに別途、大手電力は「燃料費調整額」「再エネ賦課金」が、しろくまプランは「電源調達調整費」「再エネ賦課金」が発生します。
また「しろくまプラン」は電気代が安いだけでなく、発電の際にCO2を排出しない実質再生可能エネルギーをお届けしています。切り替えるだけで、地球温暖化の防止に貢献することができます。
環境にも家計にもやさしい「しろくまプラン」への切り替えをお考えの方は「しろくまプランお申し込みページ」または以下のバナーからお申し込みください。申込ページでは、プランの詳細についてわかりやすく説明しています。